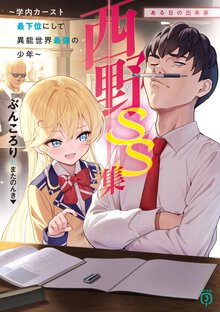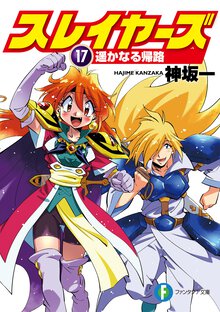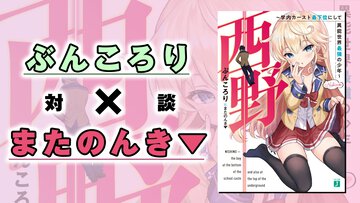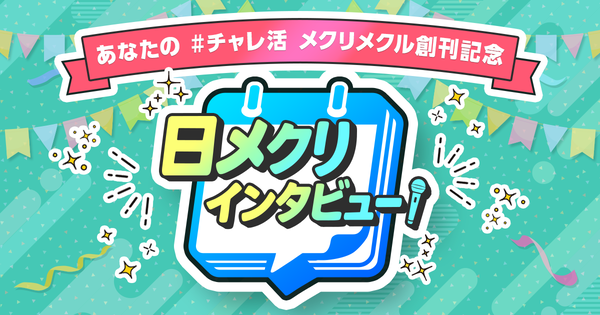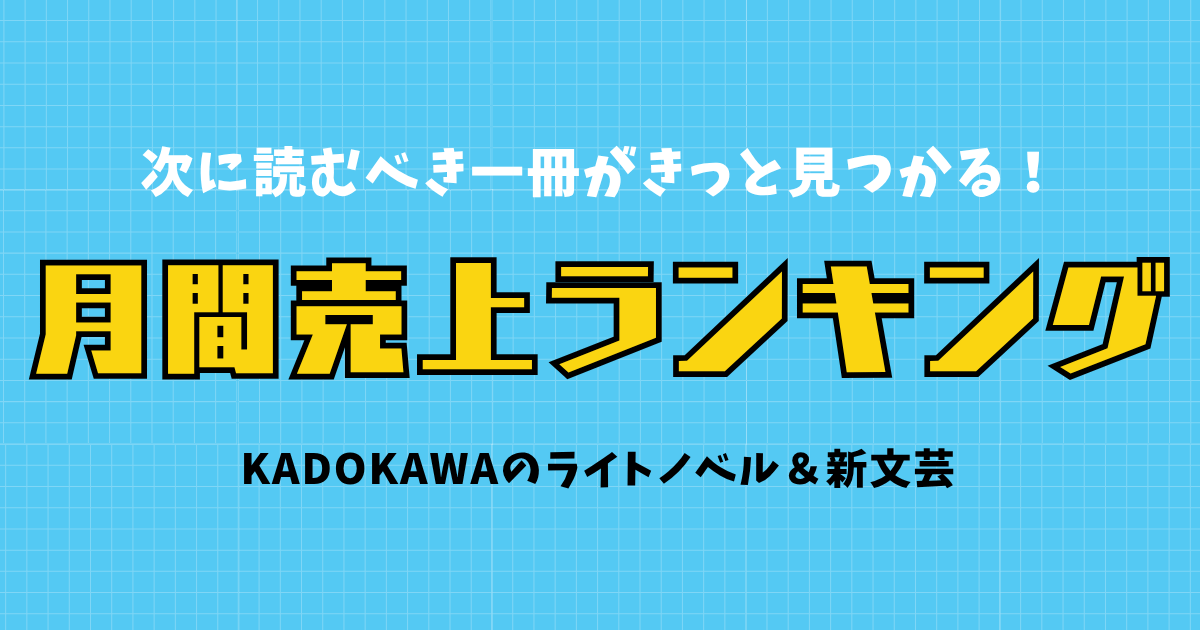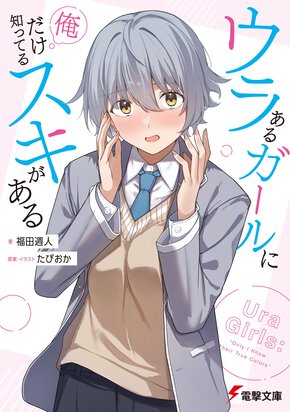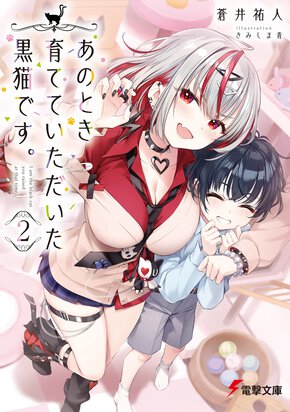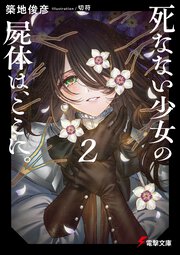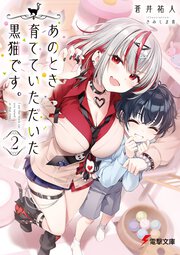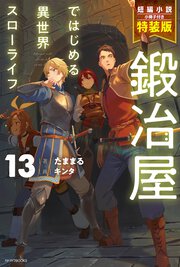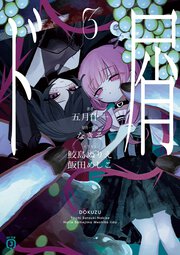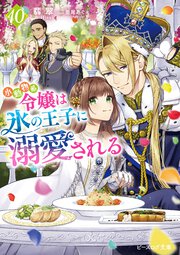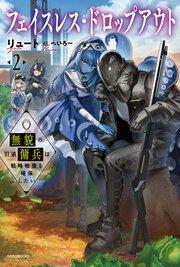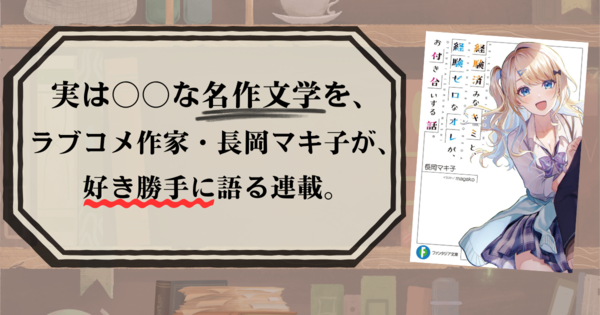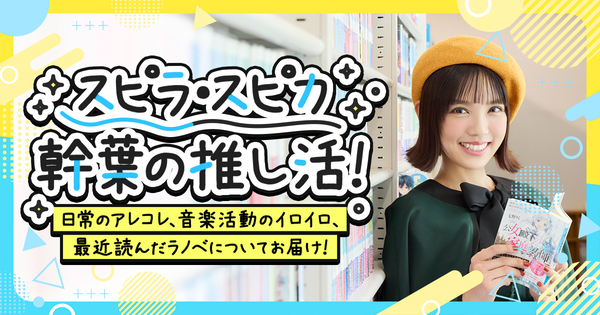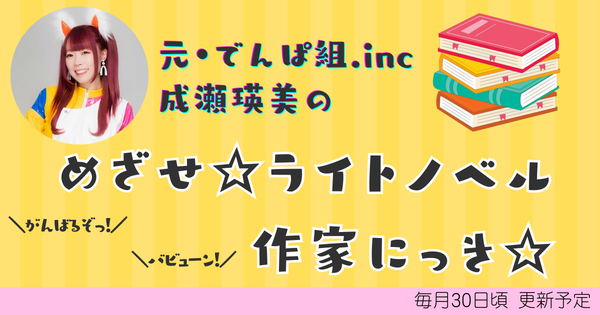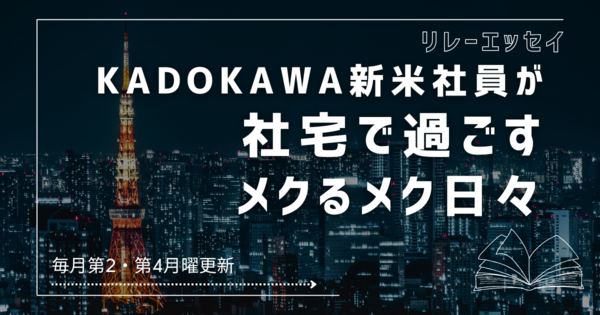ぶんころり先生の商業デビュー10周年を祝して、たくさんの方が駆けつけてくれました! これまでの作品でイラストを担当していらっしゃるイラストレーターさんたち、ぶんころり先生と関係のある作家先生・憧れの作家先生、担当編集者などなど……今の「ぶんころり」があるのはこの方々のおかげと言っても過言ではないメンバーが勢揃い。
対談6本目は、『スレイヤーズ』の著者・神坂一先生にお越しいただきました。
ぶんころり先生のライトノベル原点であり、憧れの存在である神坂一先生をスペシャルゲストとしてお出迎えということで、さしものぶんころり先生も、憧れの先生を前にいささか興奮された様子で対談に臨まれました。
ぶんころり……憧れの神坂一と初めての対談!
――今回の対談はぶんころり先生がぜひ神坂先生とお話してみたいということで実現いたしました。ぶんころり先生の今のお気持ちをお聞かせください。
ぶんころり:とても光栄に感じております。本日は貴重な機会を下さり誠にありがとうございます。自身がライトノベルにハマったきっかけは『スレイヤーズ』となりまして、神坂一先生は僕にとってライトノベルという世界の神様にも等しい存在です。
神坂一:いやいや(笑)。
ぶんころり:『スレイヤーズ』には中学生の夏頃に出会いました。当時既に「デモン・スレイヤーズ」くらいまで刊行されておりまして、本編と短編の『すぺしゃる』を追いかけている間にその年の夏休みが終わっていたことを覚えています。本当に今この瞬間が嬉しいです。
神坂一:いえいえ、とんでもございません。ご指名いただき光栄にございます。どうかよろしくお願いします。
ぶんころり:こちらこそよろしくお願いいたします。
――さっそくですが、ぶんころり先生から神坂先生にお尋ねしてみたいことがあるそうですね。
ぶんころり:いきなりの質問で申し訳ありません。スレイヤーズというとやはり、魅力的なキャラクターや世界観、ついつい考察したくなる複雑な設定がございます。神坂先生が生み出されたキャラクターは膨大なものですし、地名や固有名詞も相当な数だと存じます。自身も読む側から書く側に移ったことで、改めて先生の凄まじさを追いかけているのですが、こうした大量の命名や設定などの管理はどのように行われているのか伺ってもよろしいでしょうか?
神坂一:……ごめんなさい、管理できてません(笑)。ネーミングについては、過去キャラと名前の文字数や印象とかがなるべく被らないようにしようぐらいの意識はしているんですが、短編とかに出てくるキャラクターはポンポン忘れてるんで、ファンの方からキャラクターについての質問が来た時に「誰だっけ……?」ということは結構あります。
ぶんころり:キャラクターの名前と雰囲気がとてもマッチしていて驚かされるのですが、どのようにして名前をつけられているのか、小さい頃から疑問に思っておりました。
神坂一:何かをもじって名前をつけることもあって、原稿書きながら「名前、名前……うーん」って適当に目についた何かをもじってつけることも結構あったりするんですよ。
ぶんころり:命名の思いつきなども含めて、作家活動をする上でインプットは欠かせないと思うのですが、神坂先生は日頃どういったジャンルの作品をご覧になっていますか?
神坂一:テレビや映画や小説、漫画など他人の作品を鑑賞するのもインプットなんですけど、実は日常のあらゆる出来事が何かのヒントになると思うんです。
専門学校に通っていたころに、イラストの授業でパーティーの絵に対して先生が「登場人物がみんな画面内に綺麗に収まっているから、このパーティーは他にもいっぱい人がいるようには見えない」って批評をしたことがあったんです。それを聞いたとき『刑事コロンボ』の「カミさん」と同じだって気づいたんです。
あれは「存在はするけれど出てこないキャラクター」を設定することで、描写されている場所以外にも世界は広がっていることを匂わせてるんですね。なので『スレイヤーズ』でもリナに「郷里のお姉ちゃん」のルナの話をさせたり、ガウリイにばーちゃんの話をさせるようになりました。
ぶんころり:話が逸れていたら申し訳ないのですが、今年発売された最新刊の『スレイヤーズすぴりっと。』では、アメリアがついに姉のグレイシアと共演されておりました。本編に登場しないあのお姉さまの存在も、今言った手法と関係があったりするのでしょうか?
神坂一:グレイシアお姉様は、最初本編に登場させようとしたんですけれど、書いていてテンポが悪くなってしまったので、代理の妹として急遽アメリアが生まれたんです。それからお姉さまの正体は伏せた方が面白いだろうということで半ば公然の秘密になっていたんですが、今回の短編は久しぶりのお祭りファンサービスということで、お姉さまにも登場してもらいました。
ぶんころり:最新刊を拝見させていただいて、最初の数ページをめくった途端に20年以上前の読書体験がぶわっと蘇ってきました。今も昔も変わりのないキャラクターには感動を覚えます。こうした一貫性を保つための工夫など伺えませんか?
神坂一:やっぱり言い回しですね。このキャラクターはこういう喋り方をするよねというのをある程度イメージしておけば、場合によってはそれを逆手にとって、ギャグにするとか、一つのエピソードにもできるのでキャラクターごとの喋り方や言葉のチョイスのクセは意識しています。
神坂一から見た現在のライトノベルとは
ぶんころり:神坂先生はこれまで多彩な作品を手掛けられてきました。90年代刊行の『日帰りクエスト』では、まるで今の異世界ブームを予言するような部分もあったと思います。そんな先生の目から見てライトノベルの現在はどのように見えておりますか?
神坂一:『日帰りクエスト』の名前が出ましたが、あの当時は小説以外のゲームや漫画といったジャンルの文法や演出、面白さを小説に落とし込む、ということが行われはじめた時代で、私もそれに乗っかったんですが、今後も他のジャンルから面白い要素を輸入して落とし込むっていうのは起こると思うんですよ。そういう意味では今後も楽しみですし、今のライトノベルも嫌いじゃないです。
ぶんころり:ありがとうございます。ライトノベルを生み出された神が、今この世界をどのように見ているのかなというのが、下々の民としては気になっておりました。そのような意見を伺えてうれしいです。
神坂一:神って言い方はやめてください(笑)。いやそんなペンネームをつけたのは自分なんですけど(笑)。
――今の時代はWeb小説の感想欄やSNSを通じて読者の感想がすぐ伝わるようになっています。ぶんころり先生はこうした読者の感想をどのくらい気にしていますか? また神坂先生は自分のデビュー当時にSNSがあったら上手く付き合えていたでしょうか?
ぶんころり:僕は豆腐メンタルでちょっと辛いことを言われると心がくじけてしまうので、厳しい意見は見なかったことにして、褒めてくれる意見だけありがたく拝読させていただいています。もっとうまいやり方があれば神坂先生から是非お伺いできたらと思うのですが……
神坂一:SNSがあったらうまく付き合えていたか……無理です(キッパリ)。
ぶんころり:(笑)。
神坂一:私も他人の意見に左右されたりへこんだりしますからね。インターネットが普及した当時、編集者の方からインターネットの方がやり取りは便利だよって言われたんですけれど、「いや、自分がインターネットをやったら絶対ダメになるからやらない」って頑なに拒んでいました。今はさすがに導入してますけどSNSはやっていませんね。
ぶんころり:やっぱり、おっかないですよね。
神坂一:無理です、無理です。
ぶんころり:自分は作品のためにSNSなどで流行を調べたりもするのですが、既に過ぎつつある流行を取り入れると、その分作品の寿命が縮んでしまうので、他の作家の方はどう情報を取捨選択しているのかと悩んでいたりします。
神坂一:最近は時間の流れが速いですよね。自分が聞いた話では、登場人物が携帯で通話してる描写を入れたのに、原稿が完成するころにはすっかりスマホが普及していて、慌てて書きかえたなんて話も聞きます。一冊で完結するなら対応できるかもしれませんが、何年も続くシリーズだと難しいですよね。ぶんころり先生は現代が舞台のシリーズを書いていてそうした苦労はありませんでしたか?
ぶんころり:まさに今おっしゃっていただいた通り、前にやっていたシリーズでは、携帯っていう単語がたくさん出てきたんですけども、ちょうどスマホに置き換わる過渡期だったので慌てて全部スマホに直しました。
神坂一:やっぱりありますよね。
ぶんころり:その影響で以降では「携帯」や「スマホ」という書き方はやめて「端末」という抽象的な表記にしています。
神坂一:素晴らしい(笑)。CDもそろそろ消えそうですし、今はどんな機器が発売されて、残っていくかわからない時代で、そう考えると、すごい時代ではあるけれども怖くもありますよね。そういう意味だと、ファンタジー作品は、そのあたりがコントロールできるので、やりやすいと感じます。
ぶんころり:そこはファンタジーの強みかもしれませんね。
文章へのこだわりと、アイデアの探し方
神坂一:技術の進歩というと、紙の書籍と電子書籍というフォーマットの違いが表現に変化を生むこともありますよね。
ぶんころり:そこは本当に難しい話で。縦の一文で改行せずに読んでもらいたいなと思って書いた文章が、電子書籍だと改行されていたりしてショックだったりするんですよ。
神坂一:それはありますよね。自分も読みやすくなるように文章の密度を意識して書いているのですが、短編の場合、雑誌の掲載時には問題がなかったのに、文庫になるとみっしり詰まって、ページが真っ黒だったこともあります。
ぶんころり:そういった何気ない気配りがあるから、読みやすい文章が生まれていくんですね。とても勉強になります。
――ぶんころり先生は元々Webに作品を投稿されていましたが、Web上で文章を読みやすくするために意識した部分などはありますか?
ぶんころり:そうですね、Webには「読み飛ばす」文化があるんです
神坂一:ほうほう。
ぶんころり:文字がたくさんぶわーって並んでいると、よく読まないで先へ進むみたいな方もいらっしゃったりするんですね。そういった方でも話に乗れるように重要なテキストについては、目につきやすいように短文でポンポンポンって置いて、それに付帯する情報は、その後にドサッと並べるようにしています。
神坂一:私はWeb小説は全くやっていないので、色んなフォーマットに合わせたやり方があるんだなって勉強になります。
ぶんころり:ああ、そんな滅相もないです。もう一つ神坂先生にお伺いしたいことがありまして。
神坂一:はい。
ぶんころり:『スレイヤーズ』のあとがきで神坂先生は、自転車をこぎながら竜破斬の詠唱を考えていたというお話を書かれていたと思うのですが、小説のネタを考えるときの習慣があったらお伺いしたいな、と。
神坂一:当時の私はパナソニックの子会社の製造工場に勤めていまして、いつか作家デビューできればいいなと漠然と思っていました。それで『スレイヤーズ』の1巻となる小説をダメ元で投稿しようっていうときに、会社の行き帰りに自転車をこぎながら、ああでもない、こうでもないって呪文をぶつぶつ唱えて考えていました。
現在は乗客数が少ない電車に乗って、ぼーっとアイデアを考えたりするんですが、結局、終点に着いても何もアイデアが出ず、気がつくと奈良で鹿に煎餅をやっていたこともありました。
ぶんころり:(笑)。電車はいいですね。あのカタンカタンっていう規則的な音がなんか心に響きそうです。
神坂一:そうなんです。でも周りに人が多すぎると考えごとに集中しづらいので、最近は観光客がだいぶ増えてきてどうしようかなあって思ったりもします。
ぶんころり:大阪や奈良周りは大変そうですよね。僕も神坂先生の影響を受けて自転車に乗りながら考えたり、その延長線上でバイクに乗りながら考えたりしておりました。
神坂一:やっぱり辺りの景色が変わらないとなかなかアイデアは出てきませんよね。部屋の中にずっといると何も思いつかない。
ぶんころり:まさに仰るとおりなんですよね。先生にあやかって、これからは電車に乗りながらアイデアを考えてみようと思います。
神坂一:でも、東京近辺であまり人が乗ってこない電車って、それは普通にホラーですよね(笑)。
取材・文●柿崎憲
関連情報
『スレイヤーズ』シリーズ著者。
1989年「第1回ファンタジア長編小説大賞」において準入選、翌年『スレイヤーズ!』でデビュー。
- インタビュー
- 対談
- 神坂一
関連書籍
-
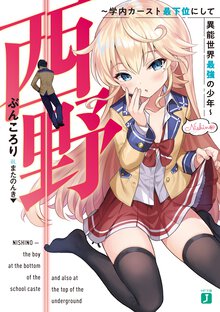 西野~学内カースト最下位にして異能世界最強の少年~【新作ラノベ総選挙2019[文庫部門第2位! このライトノベルがすごい!2019[文庫部門]新作第6位!】
西野~学内カースト最下位にして異能世界最強の少年~【新作ラノベ総選挙2019[文庫部門第2位! このライトノベルがすごい!2019[文庫部門]新作第6位!】
原作1~6巻、コミック1巻好評発売中! オーディオドラマ好評配信中!
月刊コミックアライブ&ComicWalker&ニコニコ静画にてコミカライズ連載中!
【文化祭編スタート! ぶんころり書き下ろしエピソード<ローズとカラオケ>&『僕は友達が少ない』『妹さえいればいい。』の平坂読解説収録!】
学園カーストの中間層、冴えない顔の高校生・西野五郷は、界隈随一の異能力者だ。
ダンディズムを愛する彼の毎日は、異能力を使ったお仕事一筋。
常日頃から孤独な生き様を良しとしてきた。
シニカルなオレ格好いいと信じてきた。
だが、その日々も永遠ではない。
高校二年の秋、童貞は文化祭を通じて青春の尊さに気付く。
異性交遊の大切さを知る。
これはそんな西野少年が、過去の淡白な人生から心機一転、日々の生活態度を改めると共に、素敵な彼女を作って高校生活を謳歌する為、あの手この手を用いて学園カーストを駆け上がらんと奮闘するも、一向に登れそうにない、なんちゃってハードボイルド物語(異能バトル付き)発売日: 2018/04/25MF文庫J
-
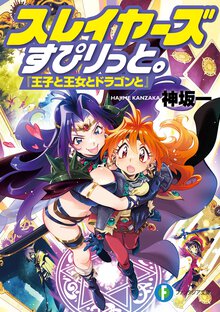 スレイヤーズすぴりっと。『王子と王女とドラゴンと』図書館をむしばむ悪(?)を成敗だ!
スレイヤーズすぴりっと。『王子と王女とドラゴンと』図書館をむしばむ悪(?)を成敗だ!
アメリアの正義感はやっぱり騒動を巻き起こし――「『王子と王女とドラゴンと』」
リナ=インバースの自称弟子あらわる!?
(金魚のうんち、もとい白蛇のナーガを添えて)――「魔法使いの弟子志願」
喪った剣の代わりを探すリナとガウリイ。
凄腕と噂の鍛冶屋が提示する、剣作りの条件とは――「魔力剣のつくりかた」
元の姿に戻る方法を探すゼルガディスは、ある男と再会する。
ちょっぴり磯臭いハードボイルド短編――「水と陸との間にて」
ドラゴンマガジン掲載の短編に、書き下ろし4編。
さらに文庫未収録SSも大盤振舞。
待望の『スレイヤーズ』短編集新刊!発売日: 2025/03/19ファンタジア文庫