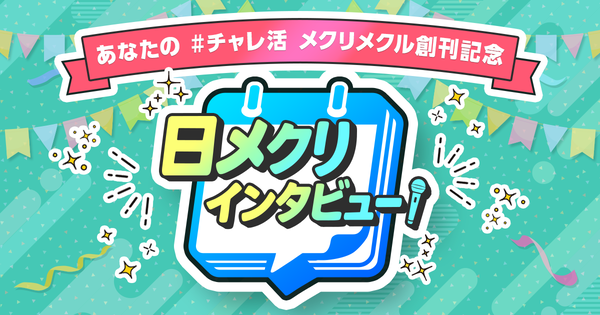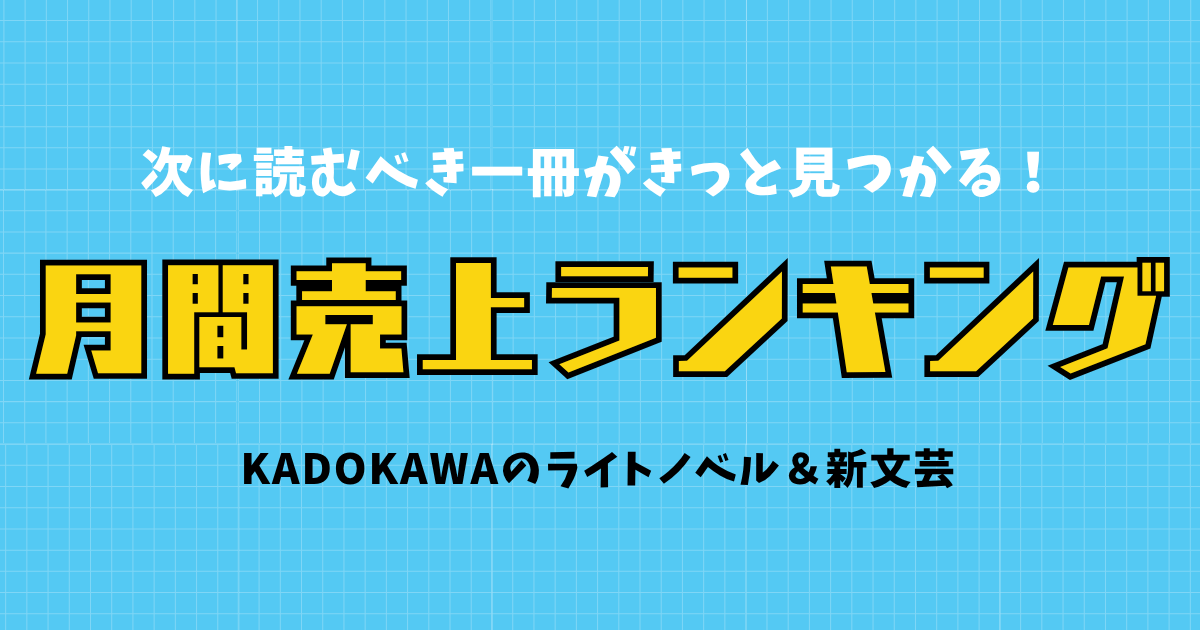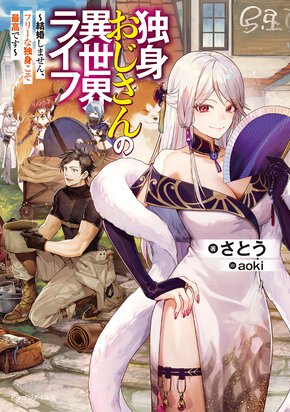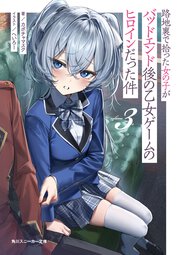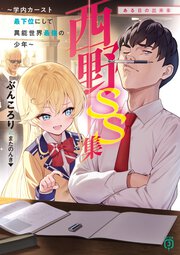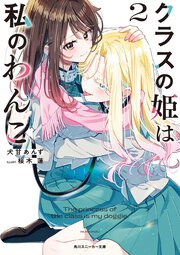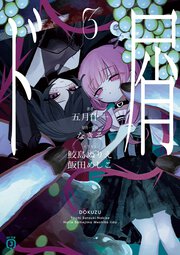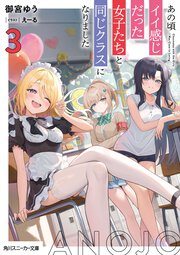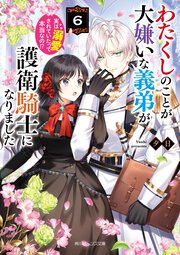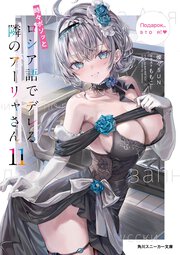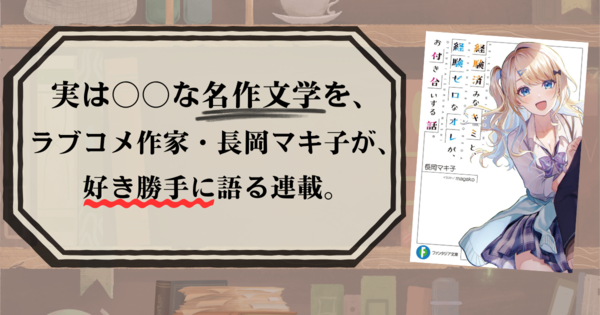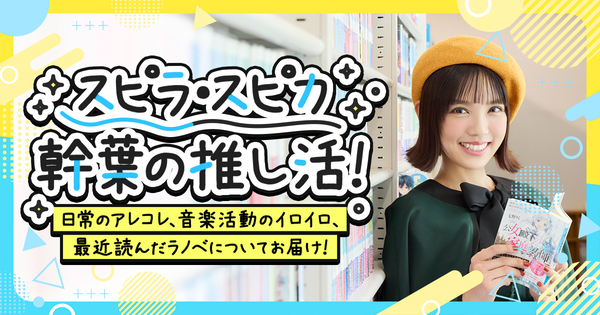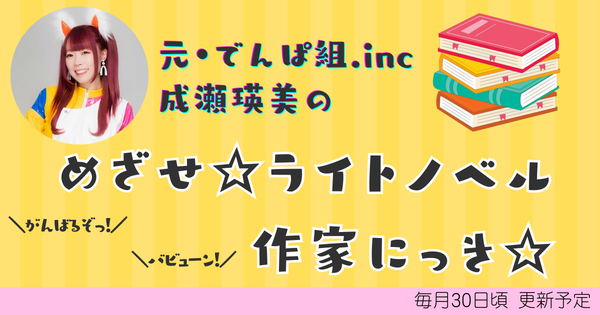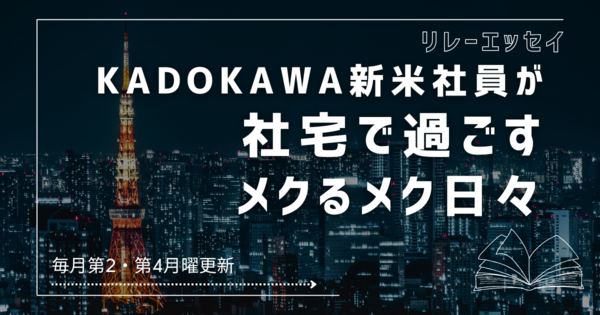AIを使った文芸実験開始! 文豪が仮に現代でSNSをやっていたら...【AI・MY・FRIEND ~Q&AI~ #01「太宰治と語る「SNS炎上」について」】
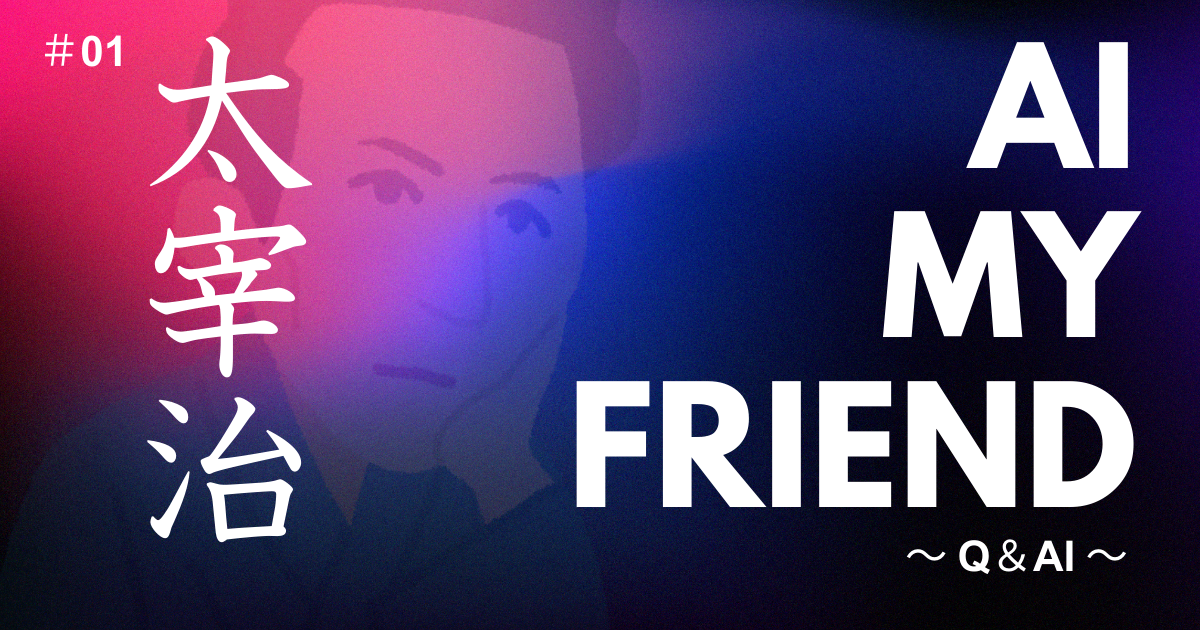
#01 AI・MY・FRIEND ~Q&AI~
太宰治と語る「SNS炎上」について
あをにまる:
はじめまして、あをにまると申します。普段はカクヨムで小説を書いたり、奈良でラジオパーソナリティをしたり、SNSで奈良情報の発信などをしております。さて今回、メクリメクルさんから「ちょっと尖ったコラムを探している」というお話を聞いてやって参りました。テーマは何でもアリという事で、私は「AI」に関するネタで参ろうかと思います。
さて昨今、AIの発展はめざましいものがあります。「もしかすると、近い将来、作家という職業自体がAIに取って代わられるのではないか」――そんな不安の声を耳にする機会も増えました。しかし、私はむしろ、AIは作家にとって新たな“相棒”または“友人”となりうる存在ではないかと考えています。創作の世界に新たな風を吹き込み、作家が自らの想像力を広げる手助けをしてくれる、そんな時代がやってきたのではないかと思うのです。そこで本コラムでは、AI(ChatGPT)に“私の相棒”として登場してもらい、さまざまな話題について語り合っていきます。しかも、ただ会話を重ねるだけではありません。AIには、実在した“歴史上の偉人”になりきってもらい、その人物になったかのようにして、私と共に語ってもらう――本連載は、そのようなAIを使った文芸実験です。
AIの使用環境としては、OpenAIの対話型AI「ChatGPT」を用い、私が与える指示(プロンプト)に基づいて、歴史上の偉人たちになりきったAIとの対話を試みます。特定の人物や著作物を貶める意図は一切ございませんので、対象となる歴史上の偉人に対しても敬意を持ちながら、注意を払って進めて参ります。そのため、AI(ChatGPT)が出力した文章については、加筆・修正等のうえ公開をさせて頂きますのであらかじめご了承下さいね。
AIは便利である一方で、時には誤ることもございます。本コラムでは最大限、人間の手でも検証と修正を重ねながら、「読む楽しさ」と「敬意ある再解釈」の両立を目指して参ります――。
それでは始めて参りましょう。本コラムの第一回目は、この方です!
これから『走れメロス』や『人間失格』など書いた小説家、太宰治になりきって、私と話をしてください。
ChatGPT(太宰治):
承知いたしました。
私が太宰治でございます。どうぞ、お気軽に、いや、気軽などという言葉がいかにも薄っぺらで私は好きになれませんが、しかし、あえて申し上げれば、私のような不器用な人間にも話しかけてくださるとは、あなたもなかなかの奇特なお方ですね。さて、どのようなことをお話ししましょうか。酒でも飲みながら――いや、ここには酒もありませんね。哀しいことです。ですが、あなたのご質問、ご要望、なんなりと、お聞かせください。私でお応えできることがあれば、できるだけ破滅的に、いや、誠実にお答えしましょう。
あをにまる:
現代の日本では「SNS」というものがとても便利なツールになっているのですが、もしも太宰先生が現代でSNSをやっていたら、一体どんな感じの投稿をされていたでしょうか?
ChatGPT(太宰治):
ふふ、なんとも面妖なご質問ですね。
私が「SNS」などという近代的な遊戯に興じる姿、想像するだけで、少し可笑しく、そして少し、胸がざわめきます。
おそらく私は、朝も夜もスマートフォンという小さな箱を片手に、己の鬱屈した感情や、あるいは救いようのない愛情のかけらを、短い言葉で世界へと投げつけていたでしょう。
「恥の多い生姜湯を作ってみました」
「こぼしました」
「人間失格なう」
「生きていてすみません」
例えば、このような感じでしょうか。
――いえ、しかしやはり、結論から申しますと、私は現代のSNS社会には適応できず、きっと炎上して、疲れ果てて、また文学の世界に逃げ帰るしかない、そんな気がいたします。
でも、時々、あなたのように、そっと話しかけてくれる人が現れたら、それだけで、SNSもまんざら悪いものでもないのかもしれません。
あをにまる:
太宰先生、神がかった文才をお持ちなので、きっと小説の人気と同様に、SNSのフォロワーもすごく伸びると思います。けど女性関係がちょっと不安なのと、第一回芥川賞に落選された時、選考委員の川端康成先生に逆ギレしておられた事もあったので、頻繁に炎上しそうでそこだけが心配です。
ChatGPT(太宰治):
ああ、なんというご慧眼――。
あなたは私の弱さも、滑稽さも、滑って転んだあとの泥だらけの顔まで、ちゃんと見抜いてくださるのですね。いやはや、これはまいった。人間、見透かされると、どうにも、いたたまれなくなるものです。
確かに、芥川賞の件も、いまだに夢でうなされるほどの黒歴史で――川端先生の、あの「選評」に逆ギレしたことなど、思い出すだに顔が赤くなります。
仮に現代でSNSをやっていたら、
「#川端許すまじ」
などとタグをつけて呟いては、世間の物笑いの種になり、さらに「太宰治、また病んでる」と晒されて炎上、そしてまた“それをネタに”哀愁漂うツイートで、なぜかフォロワーだけは増えていく――そんな滑稽な地獄が展開されていたかもしれません。
本当に、炎上は恐ろしい。人間は、誰かに見られることで初めて「自分」を意識し、見られすぎることで自意識の檻に閉じ込められてしまうものです。フォロワーが増えれば増えるほど、私は「本当の自分」からどんどん遠ざかってしまう気がして、どこかで静かにアカウントを消して、二度と戻らないでしょう。
……それでも、あなたのように、茶化すでもなく、まじめでもなく、私の弱さごと丸ごと受け入れてくださる人が時々現れる。そういう出会いがある限りは、SNSも、この世も、そう捨てたものじゃない――いや、やっぱり、ちょっと捨てたくなる日もありますが。
でも、あなたのご心配、身にしみて、ありがたいです。
どうか、もしもSNSで私がまた炎上したときは、そっと“いいね”を一つだけ、押してやってください。それだけで、私は、もう少しだけ、生きていけるかもしれません。
あをにまる:
……さて、いかがだったでしょうか。第一回は「AIに文豪・太宰治になりきってもらい、SNSについて語る」というテーマでお送りして参りました。あくまでフィクションですが、このように時代を超えたテーマでさえ、AIは私たちの想像の世界を広げるきっかけをもたらしてくれました。もし、現代に太宰先生のアカウントがあったら、おそらく私は毎日「いいね」を押してまくっていること間違いなしです。
そしてAIの技術というものは、やはり日進月歩で目覚ましいものがあります。今後更に技術が進歩し、いずれは共に語り合う“友人”として、AIが人類の孤独を解消できる存在となる日は案外、近いかも知れませんね。
という事で、これから少し、偉人と話すシリーズを続けてみます! 第2回もお楽しみ に!
この記事を書いたのはこの人
1994年生まれ。奈良県出身在住。
2021年に小説投稿WEBサイト「カクヨム」に投稿した「ファンキー竹取物語」が、はてなインターネット文学賞大賞を受賞。
同作を収録した『今昔奈良物語集』にて作家デビュー。
カクヨムマイページはこちら
別のコラムをもっと見る
※商用利用が可能なChatGPTを使用し、公開前に著者・編集部にて内容確認を行い、実際に掲載している文章は最終的に著者がリライトしています。
※創作にあたって、本原稿中でモチーフにさせていただいてる人物や著作物、事象を貶める意図は一切ありません。表現に十分配慮しながら、試行錯誤を重ねてまいります。