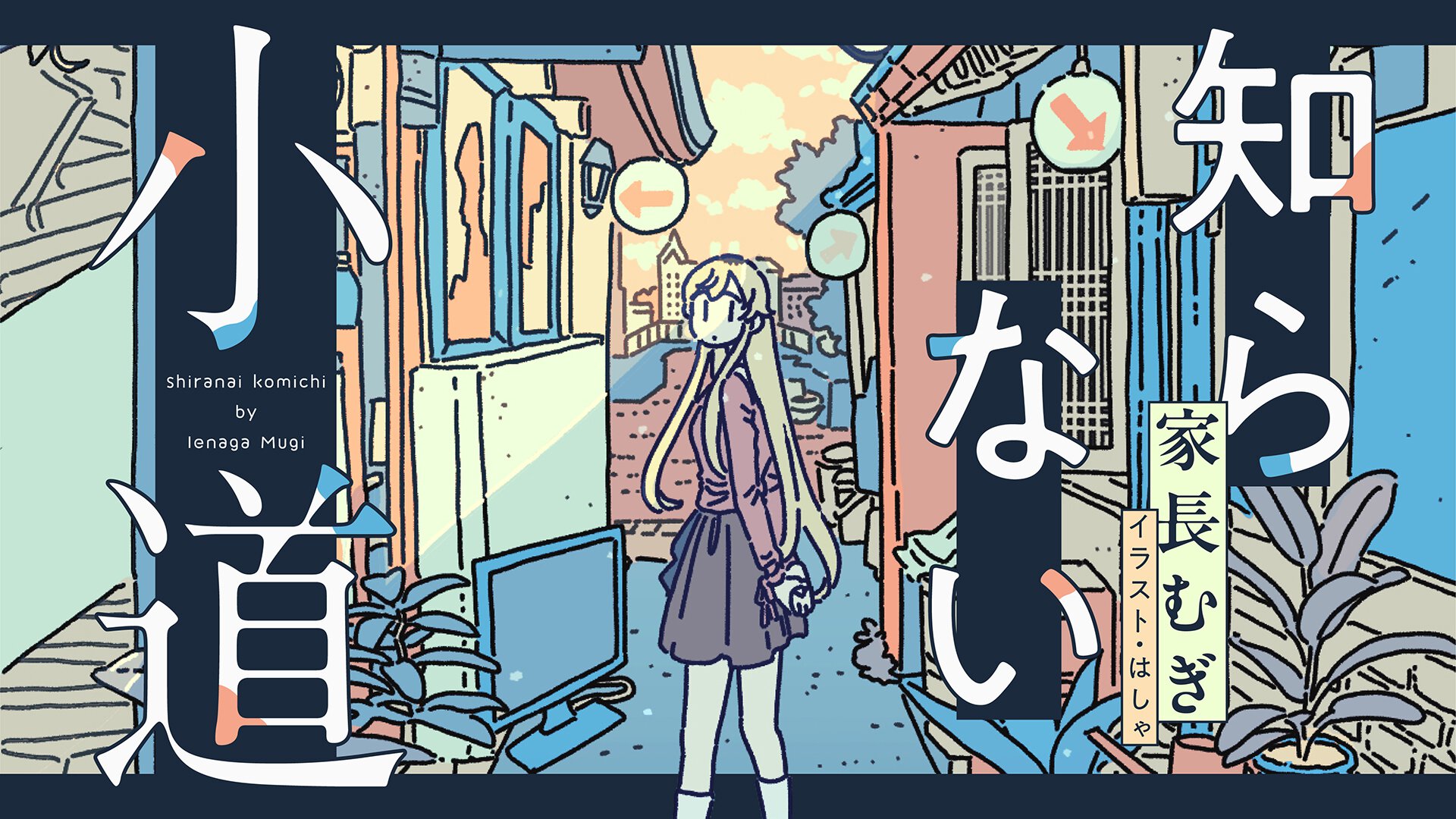02/鍼-知らない小道|家長むぎ
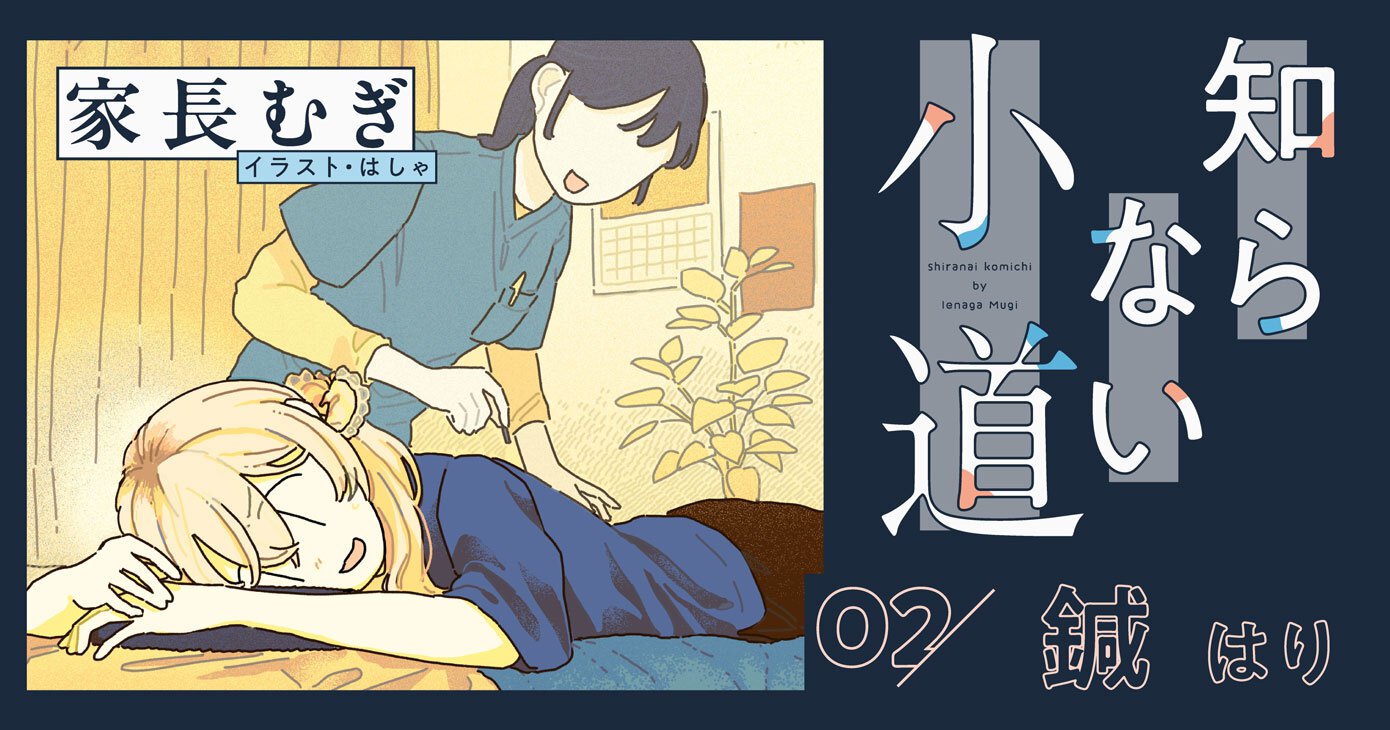
人生というものは短い――後悔をしないように、たとえささやかなことだったとしても知らぬままではもったいない。
日常に潜む“家長むぎが知らなかったもの”に触れ、初めての経験や発見を素直に綴ってゆくエッセイ。
【2025.12.14(日)公開】
鍼
胃痛のときにはじめて胃の存在が意識されると同様に……と言ったのは三島由紀夫だっただろうか。何年か前にこの言葉に出会ったとき、衝撃を受けたのを覚えている。まさに!と膝を打った。
たくさんの痛みを抱えざるを得なかった幼少期だった。
アレルギーの症状のひとつである発疹の熱っぽい痛み、少しの日焼けでも全身に感じるだるい痛み、取り除きようのない頭痛。痛みの箇所と種類を数えると本当にきりがなかった。じくじく、ひりひり、ずきずき、と痛みかたを伝えるのも得意だった。
生活では文字通り一挙手一投足に気を配る必要があった。
とくに厄介だったのはアレルギー症状そのものと、検査のための定期的な採血だ。私の原風景には、採血針を怖がって病院の廊下を必死で走って逃げ回るものの、最後にはいつも看護師二人がかりで検査室の治療台に運ばれていく幼い自分の姿がある。毎回火が付いたように泣いていた。
今思い返せば、泣きたかったのは私だけでなく両親もだろう。
不味いが値の張るアレルギー対応の粉ミルクを少ししか飲まず、卵、ナッツ、小麦、ありとあらゆるものを与えられなかったのだから(ちなみに、今はほぼ全ての食物アレルギーが治って自由な食生活を謳歌している)。
結局、針は恐怖そのものとなり「幼少期に怖かったもの」ではなく「幼少期から怖いもの」に格上げされた。
小学校の高学年になったときでさえ、学校から求められたアレルギー検査の採血が嫌で、皮膚科の待合室で2時間も泣いた。
高校生になってからも、注射や採血は極力避け、どうしても必要なときは台の上で横になった状態で処置してもらった。というのも、一度大丈夫だと思って座って採血をしたところ、気絶したからである。
だけれども、なぜか痛みにはめっぽう強い。痛いのを我慢していること自体を両親や医者に褒められながら育ってきたからだろうか、「自分は痛みに強い」という謎の自信がある。そもそも痛みに耐えつつ生活をするタイミングが多いことも関係していそうだ。
ちなみに、どれくらい痛みに強いかというと、意識がある状態での手術中に麻酔が切れたときに「すみません、麻酔が切れていると思います……」とクールに医者に申告できたくらいだ。
針は苦手なのにやたら痛みに強い人間が「はじめての経験」を探す中で異様な存在感を放っていたのが鍼治療だった。
「自分から好き好んで身体中に何本も針をグサグサと刺されたがるなんて……」という自分と「針なのに痛くないって聞いたことがあるし、健康オタクとしてやるしかない……」という自分で行ったり来たりしつつ、えいやっと初診の予約を済ませる。
人生のありとあらゆることは、えいやっとやってしまうのがポイントなのだ。
翌日、さっそく昼間の診察室で「鍼治療の始まりは、ずばり秦の始皇帝の時代です」と説明を受ける。「鍼治療がはじめてで、とにかく話を聞いて学びたいんです」と言う私に担当の鍼師はにわかに目を輝かせた。
「まあ、当時から形を変えつつも現代まで治療法の一つとして残っているということは、確実に良い効き目があるということです」
そういえば、昔の白内障の治療は針(鍼)で目を突く方法だったという。針は原始的で万能な道具だ。
私は手元の問診票に視線を落としながら相づちを打ち、印刷された人体図の頭から肩にかけてをなぞるように囲む。
「デスクワークの疲れ」と端に追記すると「普段からこってる感じがしますか?」と聞かれた。正直なところ、まだ年齢も若く「こり」みたいなものとは無縁であるような気がして「どうですかね、あまり感じないかもです」と曖昧な返事になってしまう。
いわゆる「こり」というものがよく分からない。今までなんとなく大人ぶって「今日こってるな~」みたいな適当を言っていた。もしかすると、寒気や倦怠感と同じようなたしかさで「こり」を感じる人もいるのだろうか。
1時間の治療時間のうち前半30分で整体をしてもらう。治療台の上に寝転がって身を任せるだけで、肩甲骨も肩の筋膜も正常な位置に戻ってしまうなんてすごい話だ。
そして後半30分、ついに鍼を打つときがきた。予防接種のときと同様にアルコール綿で消毒をするのだけれど、その範囲がやたらと広く「これが人間針山の気持ちか……」とそわそわする。
とはいえ、整体のおかげかリラックスできていて、「じゃあ鍼打ちますよ」と言われてものんきな調子でいられた。
まずは手の甲、親指と人差し指の付け根の部分のツボに鍼が打たれた。ちょっと痛いんかい。注射針より細い鍼だと聞いていたので、てっきり蚊に刺されるような気付かないレベルの痛みかと思っていた。
けれどたしかに、これを「痛いです!」と言ってしまうと人生は茨の道だ。だから多くの大人はこの程度の痛みは「痛くない」と割り切っているのだろう。
「5mmくらい刺さってますよ」と言われ目を開けると、たしかに左右一本ずつ、つんと針が皮膚の表面に立っている。さながらハリネズミLv.1だ。
一般的に鍼治療は「痛くはないがズーンと響く」と言われているものの、今のところはちょっと痛くて響きなし。やっぱり体がこっていないのかもしれない。
私の反応が鈍かったからか、鍼灸師は授業を再開した。
「鍼がどうやって人体に良い効果をもたらしているかというと、鍼で体の細胞を破壊しているんですね。鍼は人にとっては些細なものですが、細胞レベルでみると大破壊ですからね。その破壊された部分を修復するために血液が集まって、結果的に血の巡りが良くなるんですよ」
あーたしかに、と以前に顕微鏡で観察した玉ねぎに思いを馳せた。
玉ねぎの根っこの部分を針でくちゃくちゃに潰して、プレパラート(あの薄いガラス板)に塗りつけ、ばらばらにした細胞の分裂をリアルタイムで観察したのだった。今、私の体の中でも細胞がくちゃりとなっているだろう。
「ツボ」というのは、細胞の破壊が体にとって良いものとして作用する場所なのかもしれない。今度は言われるがままうつ伏せになった。
枕に顔をうずめた2秒後、私は“響く”を体感する。
おそらく首の付け根に4本、頭に2、3本刺さったのだけれど、一刺し一刺しが信じられないくらい重たい。ズーンじゃなくて、ズンズギャゴズズドーンだ。
鍼を一押しされると、最初に鍼が刺さったときの痛みがかき消されるように、響きが鍼を中心点として広がっていく。この感覚は初めてだ。ちくちく、きりきり、どれとも違う。これは紛れもない、“響く”だ。未知の痛覚との出会いに興奮してしまう。

「5mm刺さるだけでこんなにすごいんですね!」
「いや、これは2cm刺さってますね」
2cmかい。頭と首、貫通しちゃうよ。一体どんな入射角で2cmも入っているのだろう。
私の緊張を察したのか「まったく問題ないです、効きますよ」と笑って励ましてくれた。生殺与奪の権を握られているとはこのことだ。
ちなみに、頭と首の他に肩にも鍼を打ったのだけれど、私の肩が硬すぎて鍼が入らず「困ったな、入らないな」と鍼師のほうが動揺したときが治療時間の中でいちばん緊張した。
針が思ったように入らなかったときなんて家庭科の授業でフエルトのティッシュケースを作ったときだけだ。私の肩は重ねたフエルトくらい硬い。
驚いたことに鍼を打ち終わった後も、鍼が刺さったままの感覚は数十分くらい続いた。
整体と鍼のどちらが効いたのかはともかく、軽くなったような、けれども逆に重たくなったような、落ち着かない体で外に出る。真昼の光がまぶしくて目の奥がちりちりする。
突然、歩き慣れない住宅街の真ん中で、まるで麻酔が残っているような感覚になった。
少しぼうっとして、いつもの街がちょっとだけよそよそしい。
どうしてだろうと考えて、街が他人行儀になったのではなく、いつもの体のほうが街に馴染みすぎていたのだと思った。
都会での生活は大体の場合において、意図せず誰かの風景として生きることが多い。理由は簡単で、街の余白に滑り込むようにして、ここではないどこかを考えて、体を透明にして過ごすほうが身のためだから。
誰ともぶつからないのが肝心の日々では、とにかく馴染むことが大切なのだ。自分が街の一部であるように。
今、街は他人だ。なんてすがすがしく、よそよそしいんだろう。それに私の身体の確かさたるや。
この後いつもの私に戻ったら、肩を狭めて声を小さくして、また都市の余白で過ごすだろう。残った鍼の感覚はもうすぐ切れる。
TOPに戻る
©家長むぎ ©ANYCOLOR, Inc.
- エッセイ
- 家長むぎ