第四回:一世紀後のラブコメ作家もちょっと引いています(田山花袋『蒲団』)|実は〇〇な名作文学を、ラブコメ作家・長岡マキ子が、好き勝手に語る連載。
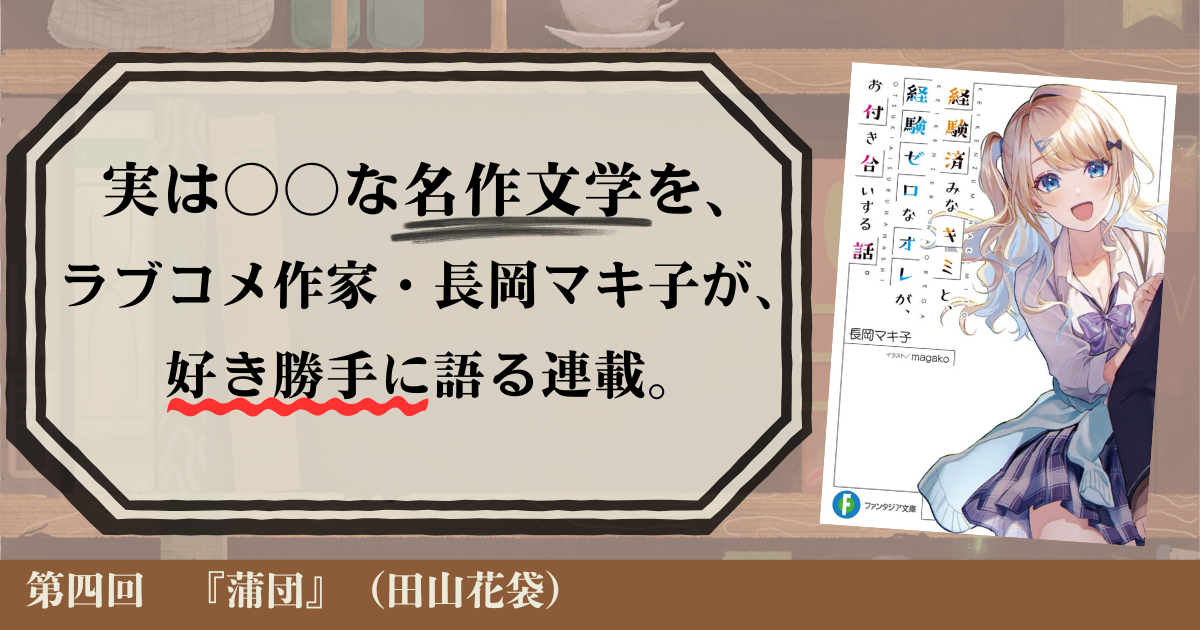
第四回目はなんと令和の世に映画化もされた、古典名作『蒲団』(田山花袋)を語っちゃいます!
第四回:一世紀後のラブコメ作家もちょっと引いています(田山花袋『蒲団』)
みなさんは「おぢ」という言葉を聞いたことがありますか?
インターネット上で「おぢ」が急速に広まったのは、2023年頃でしょう。
とある若い女性が、担当ホストに貢ぐ金を得るため、年上男性たちにあの手この手で虚偽の身の上話をして相手の同情心を誘い、彼らから多額の金銭を巻き上げた事件がありました。
彼女が自作の詐欺マニュアルで、ターゲットとなる年上男性を「おぢ」と呼んでいたため、ネット上で「若い女性に報われぬ恋心を抱くおじさん」を指す言葉として「おぢ(おじ)」が使われるようになったのです。
さあさあ! ここで本日のテーマとなる文学作品『蒲団』のご紹介ですよ!
この話、すごいんです。
文学者である妻子持ちの男性・時雄が若い女弟子の芳子に片思いするものの、芳子に同世代の彼氏ができて、勝手に失恋して芳子の蒲団の匂いを嗅ぐ話……とあらすじは身も蓋もないんですが、芳子が本当に、まったく一ミリも、時雄のことを好きじゃないんです! 小説はほぼ時雄主観で書かれてるのに、最初から最後まで、一瞬たりともイケそうなシーンがありません。
それにもかかわらず、時雄は芳子にハマっていくのです……!
これはもう、日本最古の「おぢ文学」と言ってもいいんじゃないでしょうか?
そもそも弟子入りのきっかけは芳子が時雄にファンレターを何通も書いて「弟子入りさせてくれ」と懇願したからなので、芳子も時雄を尊敬していた様子はうかがえます。
でも、マジでそれだけです。
それなのに、時雄は文通の時点から浮かれまくってます。
それから度々(たびたび)の手紙と文章、文章はまだ幼稚な点はあるが、癖の無い、すらすらした、将来発達の見込は十分にあると時雄は思った。で一度は一度より段々互の気質が知れて、時雄はその手紙の来るのを待つようになった。ある時などは写真を送れと言って遣(や)ろうと思って、手紙の隅(すみ)に小さく書いて、そしてまたこれを黒々と塗って了った。
田山花袋『蒲団』(青空文庫)より引用
写真を送れと言ってくる文学の師匠、イヤすぎる!
この続きもすごいです!
女性には容色(きりょう)と謂(い)うものが是非必要である。容色のわるい女はいくら才があっても男が相手に為ない。時雄も内々胸の中で、どうせ文学を遣ろうというような女だから、不容色(ぶきりょう)に相違ないと思った。けれどなるべくは見られる位の女であって欲しいと思った。
田山花袋『蒲団』(青空文庫)より引用
女はいくら才能があってもブスだったら男に相手にされない。作家になろうなんて女はブスに決まってるけど、どうせならギリ抱けるくらいのブスがいいなぁ! ってところでしょうか。
そこまで言ってない? いやいや、私はそういう本音を読み取りましたよ。女性作家としてはイラっとしちゃいますね!
そんなこんなで芳子は弟子になるため上京してくるわけですが、時雄の想像を裏切って、芳子は美人でした。
一方の時雄は、三人の子どもの父であり、妻は幼い子どもたちの世話で忙しく、家庭に男女の雰囲気はまるでなし。
女色に飢えていて、よく会う顔見知りの女教師のエロ妄想をしている有り様。現代だと、会社帰りに寄るコンビニのお姉さんに好意を抱いちゃうような感じでしょうか。
そんな生活を送っていたところに美人の若い女弟子が転がり込んできたもんですから、時雄はたちまち芳子に恋しちゃうわけです。
ハイカラな新式な美しい女門下生が、先生! 先生! と世にも豪(えら)い人のように渇仰して来るのに胸を動かさずに誰がおられようか。
うーん、チョロい! チョロすぎる!
そりゃ「先生!」って呼ぶでしょ、弟子なんだからさ!
読んでる最中から時雄へのツッコミが止まりません。
まあでも、この潔すぎる「おぢ」の本音こそが、『蒲団』を文学史に残す名作にした特長なんです。当時の作家はみんなかっこつけていて、おじさんのみっともない本心を書くような人はいなかったのですから。
今でもSNSでこういう発言をする男性はいますけど、大体ものすごい数の人に袋叩きにされてますからね!
それを明治時代に、権威ある文学の土俵でやったのですから、文学界の人々は、なんかすげーやつ来たな! おらワクワクすっぞ! って感じで称賛したのも納得です。
それにしても、この「おぢ」時雄、自分の心の中を素直にぶちまけすぎてハラハラします。
例えば次のシーン。芳子は田中という学生と恋仲になるのですが、時雄に対してずっと「肉体関係はない」と弁明していたのが、嘘だとバレた直後の場面なんですけど、もう読んでくださいよ。
欺かれたと思うと、業(ごう)が煮えて為方がない。否、芳子の霊と肉――その全部を一書生に奪われながら、とにかくその恋に就いて真面目(まじめ)に尽したかと思うと腹が立つ。その位なら、――あの男に身を任せていた位なら、何もその処女の節操を尊ぶには当らなかった。自分も大胆に手を出して、性慾の満足を買えば好かった。
田山花袋『蒲団』(青空文庫)より引用
お〜い、「おぢ」や!
芳子の気持ちを無視した不同意性交のことまで考えちゃってます。完全に危険思想です。
で、ここでお知らせなのですが、なんとこの作品、当エッセイではすでにお馴染みの私小説です!
それも、今まで出てきた『人間失格』や『舞姫』のような「私小説的なフィクション小説」と違って、現実との一致度がかなり高い、正真正銘の私小説です。
つまり、時雄は作者の花袋であり、芳子もその恋人も、モデルとなった人物の実名や素性まで明らかにされています。
芳子のモデルは美知代さんという方だそうですが、さぞかしびっくりしたでしょうね。師匠がそんな目で自分を見ていたことを知って……。
彼女がとりわけ鳥肌が立ったであろう箇所、最も有名な衝撃のラストシーンを読んでみてくださいよ。
芳子が出ていったあとの部屋で、芳子が使っていた蒲団の匂いを嗅ぐ場面です。
女のなつかしい油の匂いと汗のにおいとが言いも知らず時雄の胸をときめかした。夜着の襟(えり)の天鵞絨(びろうど)の際立(きわだ)って汚れているのに顔を押附けて、心のゆくばかりなつかしい女の匂いを嗅(か)いだ。
性慾と悲哀と絶望とが忽たちまち時雄の胸を襲った。時雄はその蒲団を敷き、夜着をかけ、冷めたい汚れた天鵞絨の襟に顔を埋めて泣いた。
薄暗い一室、戸外には風が吹暴(ふきあ)れていた。
田山花袋『蒲団』(青空文庫)より引用
なーにが「風が吹暴れていた」じゃい! いい感じで締めくくんな! と言いたくなるほど、その前の部分がツッコミどころ満載です。
よりによってパジャマの襟の一番汚れたところを嗅ぐのね……うんうん……わかるけど、共感したくないよ! そんなキモいこと、私小説で書いちゃうの!?
当時の文学界が震撼したのも頷けます。一世紀後のラブコメ作家もちょっと引いています。
さすが「最古のおぢ文学」、おじさんの性欲と悲哀を赤裸々に描きすぎて、もはや気まずいです。これを官能小説でなく文学の土壌でやったからこそ、この作品は評価されたのでしょう。
でも、こんな時雄ですけど、現代人目線でも評価できるところはあって、先に引用したように地の文ではまごうことなき「おぢ」思想を垂れ流す一方、実際の芳子に対する時雄の振る舞いは、道徳的で情け深く、年長男性として理想的な師匠の態度なのです。
つまり、現実世界の花袋は、女弟子の前で立派な師匠だったのです!
だからこそ、美知代さんはおったまげたでしょうね。
まさか立派な師匠が、自分が置いていった蒲団の匂いをクンカクンカ嗅いで、ムラムラ、メソメソしていたなんて!
こんなことなら女の師匠に弟子入りすればよかった、と後悔したかもしれません。
でも、当時、文学を職業にしていた人は圧倒的に男性が多かったわけで、文学で身を立てたいと思ったら男社会で生きていくしかなかったのです。まあ、今でもそういうところはありますけどね。
それで思い出したんですけどね、実は私にも、文学の師匠がいたんですよ。
もちろん弟子入りまでしてたわけじゃなくて、都心のカルチャースクールの「プロを目指す人向けの小説講座」みたいな教室に、半年間だけ通っていたことがありまして。
そこの講師の先生が、もともと文学を職業にしていた人で、たぶん私の父親くらいの年齢の男性でした。
当時の私は二十五歳。大学院を出て、塾講師のアルバイトをしながら新人賞に投稿するための小説を書く生活を送っていました。
今だったら「就職しろ!」となるところですけど、当時はまだ氷河期の出口で求人も少なく、ブラック企業の非正規社員になって好きでもない仕事に追われて薄給に喘ぐくらいなら、自由な身分でとことん夢を追いかけるのもアリなんじゃないか、みたいなノリがありました。
そうして小説教室に通い始めた私。生徒は中高年の男女が多く、私は最年少くらいの年齢でした。
授業は、生徒それぞれが書いた小説を全員で論評する、という内容で、終わったあとには先生主導で近くの居酒屋に行く流れがありました。酒好きの私はもちろん異存なく行ったのですが、先生からの詳しい講評が聞けたりするので、受講者としても有意義な飲み会でした。
お酒が入って、人見知りぞろいの作家志望者たちの会話も弾み出します。主婦の方などは授業が終わると急いで帰るので、飲み会では男性比率が上がります。
それでも、当時の私からするとおじいちゃんといえるような年齢のおじさんたちがニコニコ優しく話しかけてくれるので、居づらいということはなく、毎回楽しく飲んでいました。
そんな私の様子が気に食わなかったのか、あるとき、先生が突然「でも俺、長岡さんみたいな女性はタイプじゃないんだよね」と言い出しました。
え? と場が凍りました。そんな話、誰もしていないわけです。強いて言えば、おじいちゃん生徒さんが、私と話しながら「可愛いねぇ」と孫を見るような目で言っていたかもしれませんが……。
先生はグラスを何杯も空けて、完全に目がキマっています。「だって、長岡さんって将来太りそうな体つきしてるじゃん。俺、ガリガリの女がタイプなんだよ。◯◯さんみたいなさぁ!」と、同席していた他の女性生徒さんにまで飛び火しちゃったりして!
その後も先生は「長岡さん、あざといよ。そんな短いスカート穿いてるくせに、膝にハンカチ置いて隠したりして。若い女のそういうとこ嫌い」とイチャモンもいいとこです!
私も言われっぱなしではなく「いやいや、私は身長が167㎝あるんで、膝丈スカートでも座ったら全部ミニになっちゃうんですよ。若い女性向け用の服ってワンサイズが多いんです。ハンカチ置いてるのはスカートに食べこぼしジミがつくのを予防してるだけで、脚を隠してるわけじゃありません」と弁明しますが、先生は「とにかく俺は、長岡さんはタイプじゃない!」の一点張りで、周りのおじさんたちも「先生、それはちょっと……」と苦笑いです。
ただ楽しく飲んでいただけなのに、なぜ父親世代の先生から謎のヘイトを浴びせられなければならないのか……小説なんも関係ないやん……と、酔いも醒めて、悲しい気持ちで帰りました。
いっそ「あなたも私のタイプじゃないんで、勝手にジャッジしないでください」と言い返せばよかったのかもしれませんが、どうもそういうことが言えない性分でしてね……へへ。
結局、その一件で先生が苦手になっちゃったのもあって、次の期は受講しなかったんですけど、授業で生徒さんたちに「長岡さんの小説は漫画っぽい」と言われたことが、一般文芸ではなくライトノベルに投稿するきっかけになったので、教室に通ったことは私にとってプラスの経験でした。
そして今、先生に伝えたい。
先生、私まだ太ってませんよ! 二十年前の体重をキープしてます!
もしかしたら、あのときの先生は、私に「お前は太りやすそうだから中年になったら気をつけろよ」と親切心で忠告してくれたのかもしれない……なんて、ね?
ということで(?)、本題に戻ります!
今回『蒲団』を再読して、芳子のように師匠から好意を向けられるよりは、ヘイトを向けられる方がマシだったのかなぁ……なんて思ったりしましたとさ!
今も昔も、若い女性というものは、ただ普通に生きているだけで、勝手に好かれたり憎まれたりしてしまうようです。
最近の結婚相談所なんかでは、中年男性が二十代女性にお見合いを申し込むことを「おじアタック」と呼んで、仲介人がブロックすることもあるそうですよ。
同世代の魅力的な男性とマッチングしたいと思って入会した若い女性にとって、おじアタックは迷惑行為のようです。
この作品を読むと、それは昔も同じだったのだなぁと思わざるをえません。
おじさんは若い女性にドリームを抱き、夢破れたのちに女の残り香を嗅いで泣く……そんな現実と地続きの生々しさと悲哀を味わうのが、『蒲団』の醍醐味なのです。
この作品はラブコメ的に見れば失恋モノですが、その想いは完全なる一方通行で、そもそも何も始まっていなかったのですから。
そう考えると、お金を奪う代わりに夢を与え続けてくれた冒頭の事件の女性は、もしかしたら「おぢ」にとっての救世主だったのかもしれません。
しかし、これほどおぢおぢ言ってしまったあとで恐縮なんですが、実は主人公の時雄、作中でまだ三十四、五歳くらいなんですよ。
だとしても、二十歳そこそこの芳子にとって一回り以上年上の既婚男性は恋愛対象外だったでしょうけど、現代の感覚だと、三十五なんて全然若者ですよね? 今の私より十近く年下です。
なんなら、それくらいの年齢の男の子に、酔っ払って「若いね〜、彼女いる?」なんつってコンプラぶっちぎりのウザ絡みしてる私自身が、言い逃れできないほどの「おぢ」です! 面目ない!
くれぐれも、息子ほど年の離れた若者に向かって「タイプじゃない」なんてことは言うまいと、心に固く誓うのでした。
長岡マキ子(ながおか・まきこ)
1982年、東京都生まれ、埼玉県在住。慶應義塾大学院文学研究科修了。第21回ファンタジア大賞にて金賞を受賞しデビュー。代表作は『経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。』。『蒲団』の芳子が現代を生きてたら、飲み仲間の男性を引き連れて深夜までハシゴ酒する女性作家になってたんじゃないかなぁと思います。いや、それ私のことなんですけどね。
アイコンイラスト/みかきみかこ































