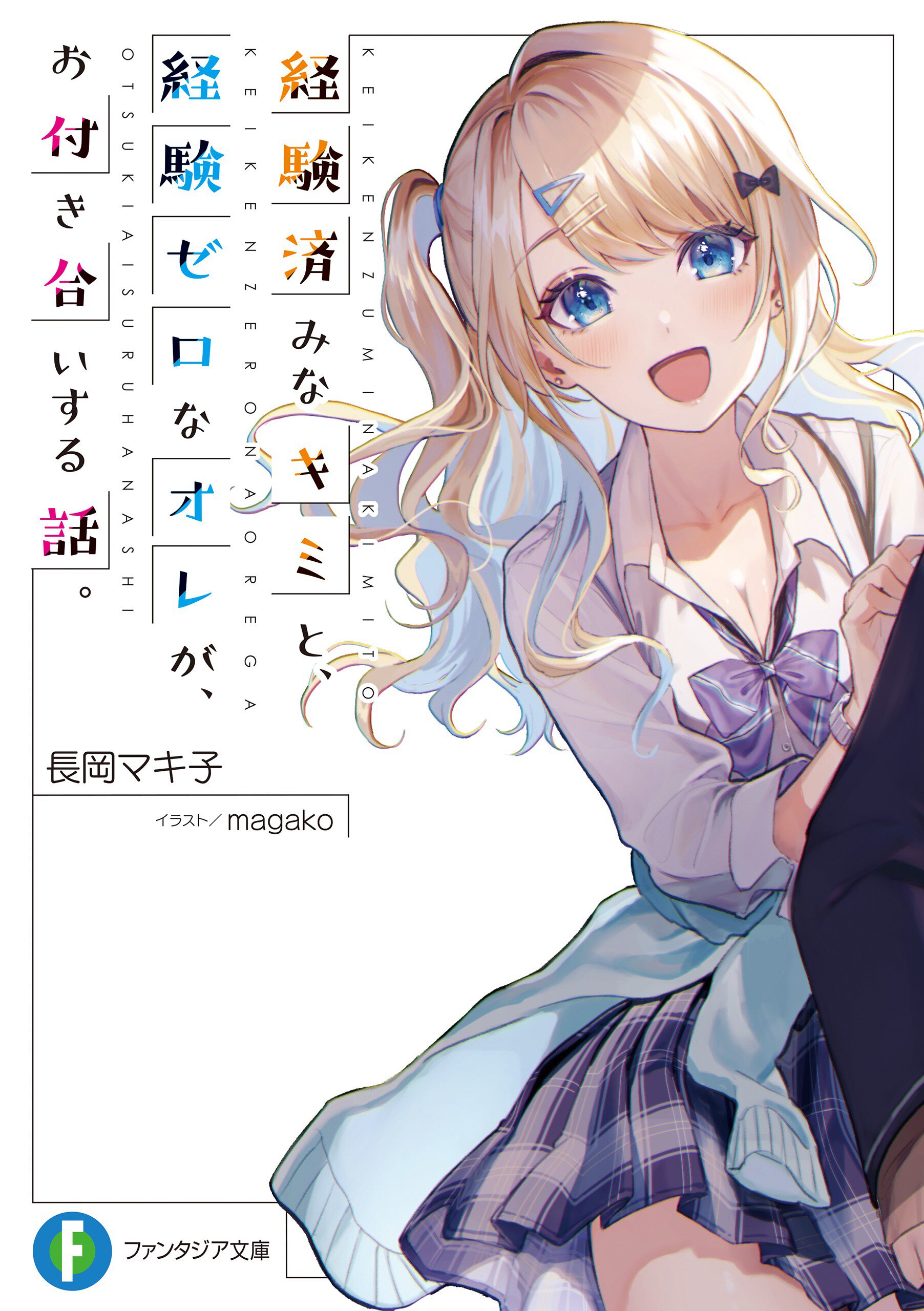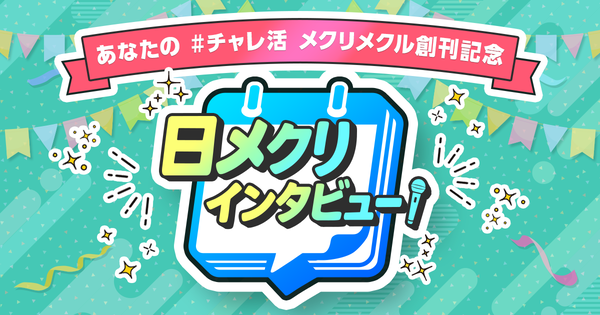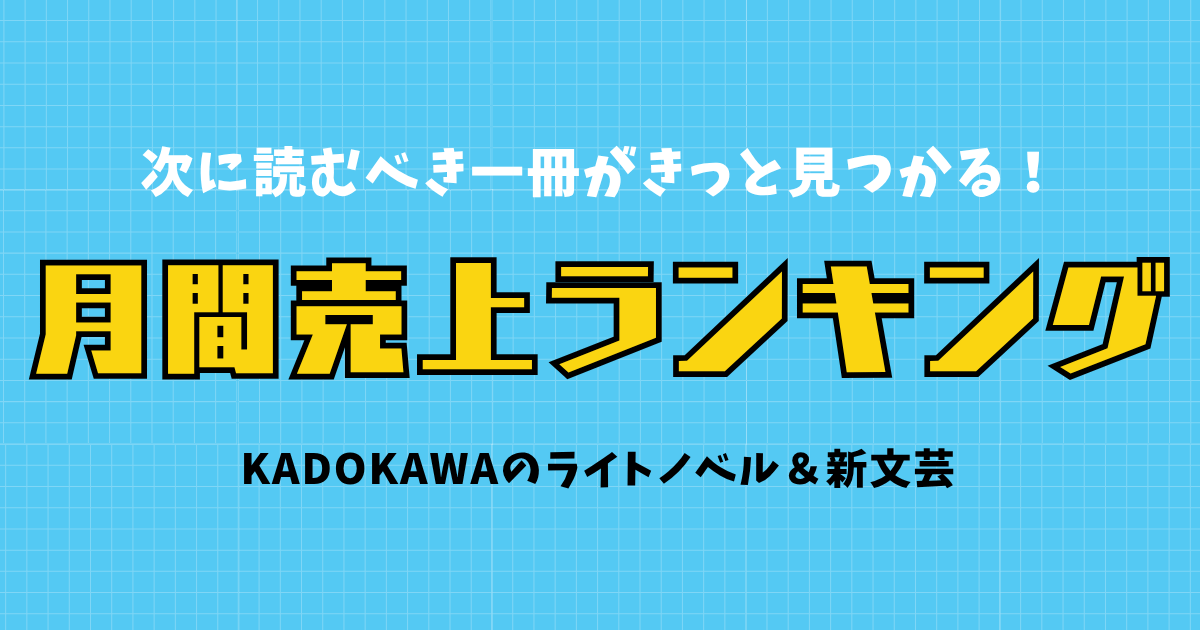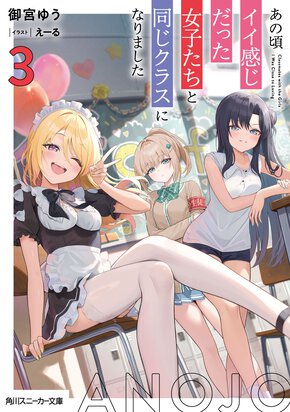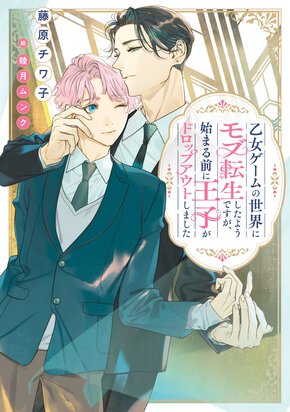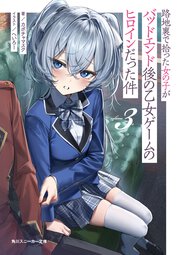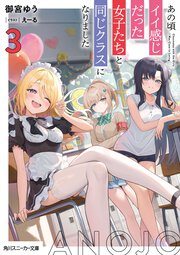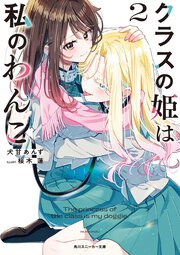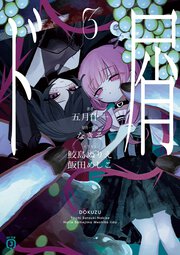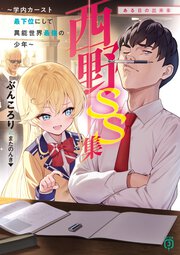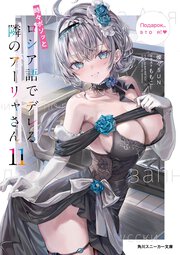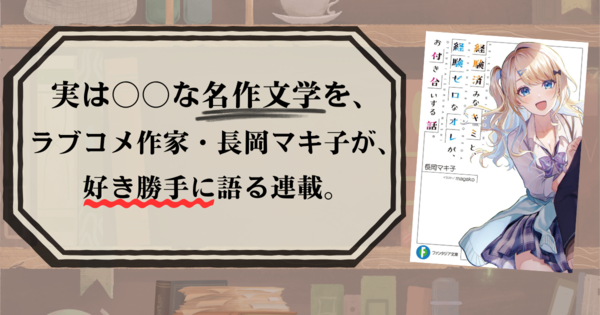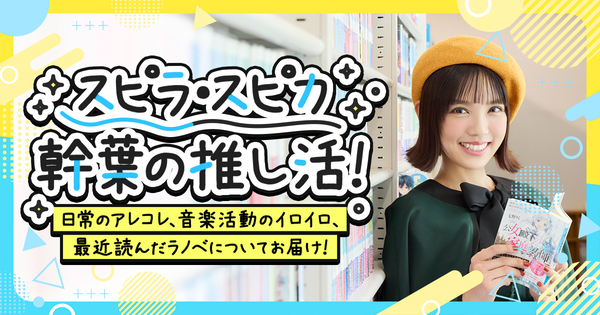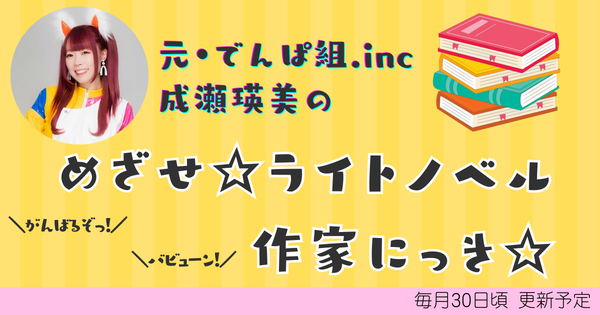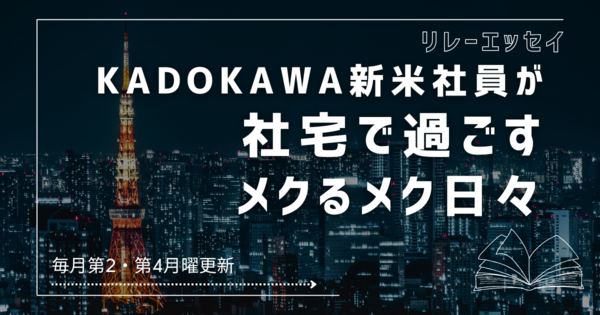第二回:せめてどちらかだけでもBSSのわかり手だったら(夏目漱石『こころ』)|実は〇〇な名作文学を、ラブコメ作家・長岡マキ子が、好き勝手に語る連載。
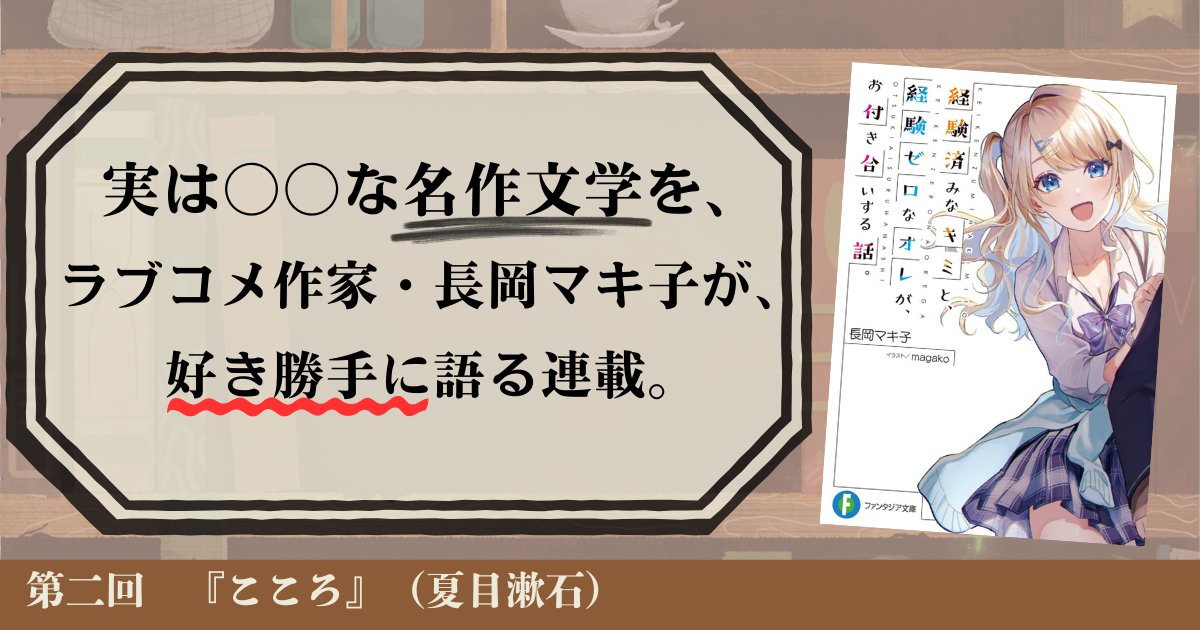
第二回目は知らない人はいない、あの超名作『こころ』(夏目漱石)を語っちゃいます!
第二回:せめてどちらかだけでもBSSのわかり手だったら(夏目漱石『こころ』)
突然ですが、みなさんはBSSという用語をご存じでしょうか?
私は初めて聞いたとき、2000年代まで流行っていたネットの掲示板のことかと思いました。それはBBS!
そんなインターネット老人会ネタはさておき、BSSというのは「僕が」「先に」「好きだったのに」の頭文字をローマ字にしたもので、片思い中の女性を他の男に取られる展開を表すネット用語のようです。
同じような成り立ちの用語で、もっとメジャーなものに「寝取られ」を示すNTRがありますが、こちらは文字通り「恋人や妻を他の男に寝取られる」展開です。「寝取り」側に感情移入すれば「他の男の女をモノにしている」優越感があるし、「寝取られ」側には「僕の彼女が他の男に……!」という嫉妬が、興奮の燃料になっていることが想像されます。
対して、BSSは「ただ先に好きになっただけ」。
つまり、片思いしていた女性が、ぽっと出の他の男に奪われていくのを見ている状態で、奪われた側は、それに憤る権利を有していない。ぽっと出の男の方は、ライバルがいた認識すらないかもしれません。
なので、BSSは「僕が先に好きだったのに……悔しい! なぜもっと早く行動しなかったんだろう」という自己嫌悪や、「でも、他の男の手でメスにされていく彼女の姿に興奮してしまう……!」という倒錯的な情緒を内包した、NTRよりも精神的なマゾヒズム傾向の強いジャンルのように思われます。
のっけからオトナな話ですみません!
しかし、今日ご紹介する夏目漱石の『こころ』は、まさにこのBSSを題材にしていると言える作品です。
本作を掲載する高校の現国の教科書は現在も多く、最も有名な近代日本文学作品の一つと言っても過言ではないですよね。
ということで、今回もラブコメ作家視点から、この作品を見ていきたいと思います!
改めて説明するまでもないかもしれませんが、『こころ』は、主人公の「私」が、学生の頃に「先生」と呼んで慕っていた年上の男性について、先生亡きあとに、往年の先生との会話や出来事を振り返ってまとめた二つの手記パートと、先生が自殺前に書き遺した「遺書」を全文掲載するパートで構成される小説です。
有名なのは、この「遺書」に書かれた、先生の学生時代の恋物語でしょう。
先生は下宿先のお嬢さんに片思いする一方で、家庭に恵まれない同郷の友人Kを同じ下宿先に住まわせます。しばらくして、Kからお嬢さんに対する恋心を打ち明けられ、先生は動揺しながらも、Kを出し抜くためにお嬢さんの母に直談判して、お嬢さんとの結婚話をまとめることに成功。二人が結婚することを知ったKは自死する――そんな展開です。
どうですか? これ、まさにBSSじゃないですか?
さらに地獄なことに、先生はKに自分の気持ちを一切打ち明けず、突然結婚発表をかましていくストロングスタイルで立ち向かうので、Kの立場からすると、先生がいつからお嬢さんを好きだったのか、そもそも恋心があったのかどうかもわからず、なんとK視点から見てもBSSが成立してしまうのです!
それにもかかわらず!
この二人、どっちも絶望的にBSSの才能がありません。
冒頭で説明した通り、BSSの醍醐味は、ひそかに片思いしていた相手をぽっと出の男に奪われることへのせつなさや自己嫌悪などの感傷を味わい切るか、さらに発展して、自力で見ることのできなかった意中の相手の艶かしい姿に萌えることにあります。
しかし、この二人は、どっちもその醍醐味を享受しようとしません。
それどころか、高学歴童貞丸出しの全力パワープレイでBSS状況を粉砕しにかかるのです。
先生は、Kよりも先にお嬢さんと結ばれるために、お嬢さんをすっ飛ばしてお母さんの方に話をつけて結婚話をまとめ。
Kの方は、二人が結婚することを知ってすぐに自殺します。
こうして二人は、各々のやり方でBSSをキャンセルしました。
そして結局、先生も時間差で自殺します。Kの自死により、自身の行いに生涯消えない罪の意識を植え付けられたためです。
どうしてこうなった……。
ああ……先生とK、せめてどちらかだけでもBSSのわかり手だったら……!
先生が、Kとお嬢さんがじわじわと親密になっていく過程を見守りながら「僕が先に好きだったのに……」と感傷に浸る道を選べれば!
Kが、先生とお嬢さんが結婚してからも下宿し続けて、夜な夜なこっそり新婚夫婦の営みを盗み見ては「僕が先に好きだったのに……」と、胸と身体の一部を熱くする才能を有していれば!
こんな悲劇は起こっていなかったのに……。
まあ、そんなBSSおじさんな先生に「私」が惹かれるかは疑問なので、その場合はこの小説自体が成り立たなかったかもしれませんが。ガハハ!
ハッピーエンドラブコメ大好きの私としては、先生とKには、ぜひともBSSの萌えを会得してほしかったなぁと思ったりするわけです。
果たしてBSSエンドが真のハッピーエンドなのかという疑問はありますが、双方自死エンドよりは……ね?
命あっての物種、なのですから。
ところで、先に少し触れましたが『こころ』は上・中・下の三つに分かれていて、ここまで話題にした内容はすべて「下」に当たります。
それぞれのパートを簡単に説明すると、「上・先生と私」は、主人公である「私」が在りし日の先生との交流について振り返る手記として書かれており、その内容を引き継ぎながらも「私」が先生から離れて故郷に帰り、重病で死を待つ父を看病しながら過ごした日々を振り返る「中・両親と私」、そして、そんな日々の最後に先生から届いた遺書の内容を記した「下・先生と遺書」という構成になっています。
あまり話題にならない「上」「中」の方が、作品全体のウェイトは重いんですね。
これは小説家として実感することですが、作家は作中に無意味な文章は書きません。読者が「ここのくだり長いし、つまんないなー」と読み飛ばすような部分があったとしても、作者本人には何かしらの意味があって書いた文章です。
それは個人的な思い入れによって筆が乗ってしまった箇所かもしれないし、作品のために必要な描写かもしれません。
前者の場合は、編集者から指摘を受けて「確かに、読者には興味ない部分かも」と反省して削ることが多いです。
なので、漱石ほどの小説家が、作品にとって重要でないパートを、そんなに長々書くとは思えないわけですよね。
そもそも、先生の人生について書きたいのなら、先生を主人公にした方がストレートに伝わりますよね? それをあえて「私」視点で書いたのだから、『こころ』はあくまでも「私」の物語なのです。
『こころ』を「私」の物語として読み解いたとき、「上」「中」で描かれていることは、東京で大学生活を送る中で近代的な自我を確立しつつある「私」が、前時代的で教養のない田舎の父を心の中で見限り、自身の新たな模範となってくれそうな謎多き先生を慕う、という構図になっています。
そんな「上」「中」を読んで、「下」で先生の遺書を読み進めるうちに、不思議な感覚に襲われるのです。
遺書の中に出てくる学生時代の先生の思想や言動が、「上」「中」の手記を書いた「私」と同一人物のもののように感じられてくるのです。
これは漱石が登場人物の主観の書き分けができていないということではなく、おそらく意図的な相似です。
学生時代の先生は、学生の「私」に似ていた。
この事実は、人嫌いの先生が、なぜか「私」からの好意をすんなり受け入れ、懐に入れるような付き合いを始めたことへの理由づけにもなります。
そして、先生にとっての「私」の存在にも意義が発生します。
Kの自死によって変わってしまう前の自分自身によく似た若者である「私」と出会ったことで、墓場まで持っていこうと思っていた自身の秘密を打ち明け、彼の中で教訓として活かしてもらう希望を見出したのです。そのために自分の人生を完結させる必要があるとしても……。
さらに私は、読書中にもう一つ、別の違和感に行き当たりました。
それは「私」が先生の奥さんについて語るときの、妙な言い訳がましさです。
「先生の奥さんにはその前玄関で会った時、美しいという印象を受けた。それから会うたんびに同じ印象を受けない事はなかった。しかしそれ以外に私はこれといってとくに奥さんについて語るべき何物ももたないような気がした。
これは奥さんに特色がないというよりも、特色を示す機会が来なかったのだと解釈する方が正当かも知れない。しかし私はいつでも先生に付属した一部分のような心持で奥さんに対していた。奥さんも自分の夫の所へ来る書生だからという好意で、私を遇していたらしい。だから中間に立つ先生を取り除(の)ければ、つまり二人はばらばらになっていた。それで始めて知り合いになった時の奥さんについては、ただ美しいという外(ほか)に何の感じも残っていない。」夏目漱石『こころ』青空文庫 より引用
どうです?
「語るべき何物も持たない」相手の説明にしては、長くないですか?
これも感覚ベースの考察でしかありませんが、なんとなく「(今はそうじゃないけど)このときはなんとも思ってなかったんですよ!」という弁解のように読めてしまうんですよね。
ここで改めて確認しておきたいのは、この手記パートを書いている「私」は、先生の死後からある程度年齢を重ねているであろう描写がある点です。
それに、こんな一文もあります。
「子供を持った事のないその時の私は、子供をただ蒼蠅(うるさ)いもののように考えていた。」夏目漱石『こころ』青空文庫 より引用
わざわざこんな書き方をするってことは、今の「私」は結婚して子どもがいるんだろうなー、ふーん……。
そして、ふと思ったんですよね。
この手記を書いている現在の「私」は、もしかして先生の奥さんと家庭を持っているんじゃない? と。
想像してみてください。作中にはそこまで書かれませんが、先生から遺書をもらって東京に帰った「私」は、先生の自殺を受けて嘆き悲しむ奥さんと再会したことでしょう。先生の死の真相を知る唯一の人間として、自分を責める奥さんに「あなたのせいじゃないです」と言葉をかけて慰めたりして。先生の死から時間が経過した頃には、在りし日の先生の思い出話なんかをして、二人で笑い合って……。
おやおや? なんだかラブな雰囲気になっていきそうな気がしませんか?
ただでさえ「私」は奥さんのことを「美しい人」と思っているのだし、奥さんは先生より年下なので、「私」の恋愛対象にならないほど年齢が離れているわけではないでしょう。しかも「私」の内面は、奥さんが「お嬢さん」だった頃の先生に似ているのです。
気になったので調べてみたところ、主人公が奥さんと結婚した説を唱える研究者はいるようで、あながち私のラブコメ脳が生み出した荒唐無稽な妄想ではなさそうです。
参照したのは、石原千秋『『こころ』で読みなおす漱石文学 大人になれなかった先生』(朝日文庫/朝日新聞出版)という本ですが、先生の奥さんと今の「私」が結婚していると考えられる根拠を詳しく解説しているので、気になった方は読んでみてはいかがでしょうか?
何より『こころ』の面白いところは、手記を書いている現在の「私」の状況がほぼ書かれない一方、先生と過ごした当時の状況や心境などは微に入り細を穿って描写されているため、空白の答えがその中にある気がして、読者がつい精読して考察してしまう余地がある点だと思います。
なので、私はこの作品を、次のように考察します。
『こころ』を「先生」目線のラブコメとして見たら……「BSS展開をキャンセルしたら親友が人生キャンセルしてしまい、罪悪感から僕も人生キャンセル……死後の現世で最愛の妻は僕を慕ってくれていた若者にNTRれました!」という、ここから人生二周目が始まらなければやってられなさそうなドカ鬱ストーリーだと!
とはいえ、先生は、自分亡きあと、妻が「私」のものになることも、ちゃんと折り込み済みだったのではないかと思います。
そのヒントになる箇所が「上」にあります。「私」が先生の家を訪れた際、先生は妻と以下のような会話をするのです。
“「静(しず)、おれが死んだらこの家(うち)をお前にやろう」
奥さんは笑い出した。
「ついでに地面も下さいよ」
「地面は他(ひと)のものだから仕方がない。その代りおれの持ってるものは皆(みんな)お前にやるよ」”
夏目漱石『こころ』青空文庫 より引用
このときに先生が持っていたものの中には、当然ながら「私」からの多大な関心もありました。
先生が「おれの持ってるもの」と言ったとき、頭の中に浮かんでいたものの中には、目の前にいる青年「私」も入っていたと考えるのが自然ではありませんか?
先生は、自分が幸せにすることのできなかった最愛の妻を、かつての自分によく似た若者に託したように思えます。
それが先生にとっての贖罪だったのではないでしょうか?
そう捉えたとき、主人公の「私」視点で見た本作は、次のような意義を持つものになります。
若き先生が、親友を死に追いやるほど愛した女性・静を、先生亡きあとに手に入れ、彼女との間に子を成し、温かな家庭を築いた「私」が、成熟した大人の男としての視点から「私がかつてあんなにも惹かれた先生とは、一体何者だったのか」という問題と向き合うために書いた手記――それが『こころ』という小説の全貌であると。
いやぁ、漱石ってほんとすごい物書きですね。さすがは文豪。
こんな読み方もできるなんて、高校の授業で初めて『こころ』を読んで、女子校に数多生息する腐女子の友人たちと「先生とKのBL、どっちが受でどっちが攻?」を議論し合っていた頃には、想像もしませんでしたよ!
そんなこんなで今回も好き放題語らせてもらいましたが、このエッセイを読んだラブコメ好きのあなたが、今、ほんの少しでも『こころ』を冒頭から読み直したい気持ちになっていたら、それが私の本懐です。
長岡マキ子(ながおか・まきこ)
1982年、東京都生まれ、埼玉県在住。慶應義塾大学院文学研究科修了。第21回ファンタジア大賞にて金賞を受賞しデビュー。代表作は『経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。』。漱石がビール一杯で真っ赤になるほどの下戸で、紅茶には砂糖をたっぷり入れる派の甘党だったのを知り、思わず真顔になってしまった酒豪の無糖コーヒー党です。
アイコンイラスト/みかきみかこ