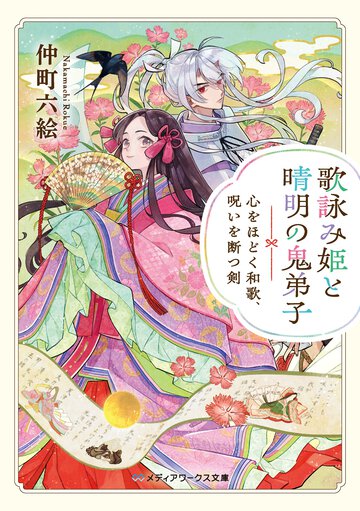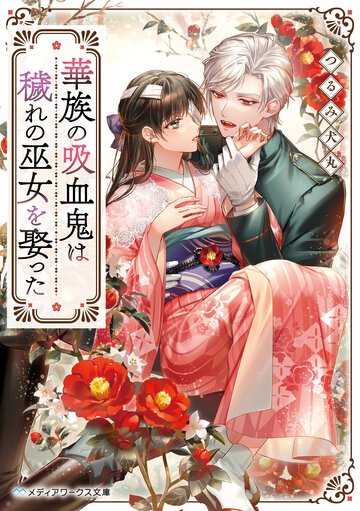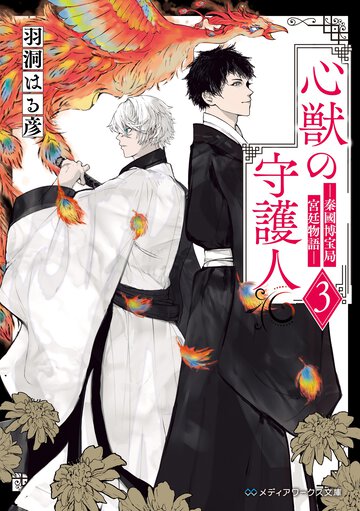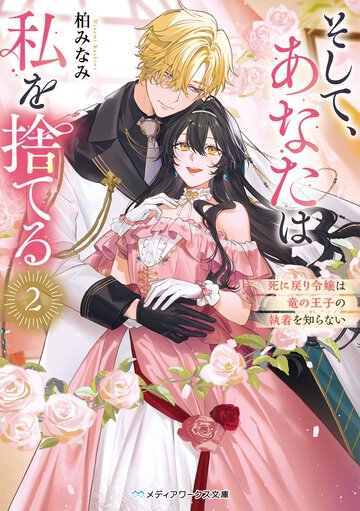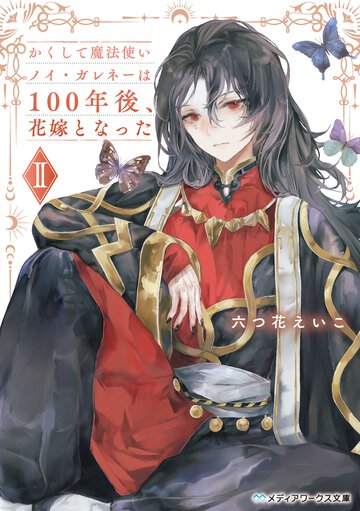さくらが咲いたら逢いましょう
発売日 :
2018/03/23
永遠の桜の下で紡がれる、出会いと別れの物語。
桜の名所・千里町に古くから語り継がれる言い伝え――それは、時を超えて大切な人との『縁』を結ぶ“トキノサクラ”の伝説。
季節は春。五歳の悠希は、満開の桜の下で歌う名前も知らない歌姫と出逢った。
「あなたの未来を、教えてあげるから」
桜が咲く間だけ姿を現す彼女は、悠希の悩みを未来を見通すように言い当ててしまう。
それから春が巡り、高校生になった悠希が入部した合唱部には、あの歌姫にそっくりな顔をした女の子がいて……。
永遠の桜に導かれた出逢いと別れの奇跡が交差するとき、きっとあなたは“涙”する。
季節は春。五歳の悠希は、満開の桜の下で歌う名前も知らない歌姫と出逢った。
「あなたの未来を、教えてあげるから」
桜が咲く間だけ姿を現す彼女は、悠希の悩みを未来を見通すように言い当ててしまう。
それから春が巡り、高校生になった悠希が入部した合唱部には、あの歌姫にそっくりな顔をした女の子がいて……。
永遠の桜に導かれた出逢いと別れの奇跡が交差するとき、きっとあなたは“涙”する。
- レーベル: メディアワークス文庫
- 定価: 715円(本体650円+税)
- ISBN: 9784048936927
メディアワークス文庫の新刊
みんなのレビュー
-
coco夏ko10角2020/03/0121千里町に語り継がれているトキノサクラの伝説。千里自然公園いいな、透き通った桜の花びら…。きれいだ。
-
ギンちゃん2019/03/2317これからの季節にぴったりのお話でした。時を越えても結ばれている人の想いとその縁。桜にはこういう奇跡を起こせそうだし、そんな言い伝えがもし自分の暮らす町にあったなら素敵だと思う。熊谷さんと沙樹さんのこれからが優しい時間になるといい。
-
やまと2018/04/078時も生死も超越して人との縁を結ぶとされる"トキノサクラ"が奇跡を起こす千里町。そんな町でたくさんの人たちの絆と想いが交差する連作短編集。悪くはないけど…という印象でした。人と人との繋がりが生まれる瞬間は誰にもわからない。だからこれから新たに出会うであろう人たち、そして今現在自分の周りにいてくれている人たちを大切にしなくてはいけないと思わせてくれる作品でした。また、作中の「言葉の方が先行して、心を縛っているのかもしれない」という言葉がとても印象に残りました。
-
ブー2018/05/274良かったです。桜と縁を中心としたハートフル・プチファンタジー!5話からなる物語で、現代がら未来にかけて「トキノサクラ」を中心に縁に関わる人々の物語。個人的にですが、桜のイメージ「生と死」「出会いと別れ」と人の縁を上手く物語した感じが良かったです。桜の頃再読したいですね。
-
siro2025/08/143★★★★★/シンプルで良かったかな。桜を通して過去と未来が繋がっているという要素は、とても日本人的な感覚で読んでいて心地よい。桜の樹の下には死体が埋まっているという、どちらかといえば悪的なことについても、死んでしまった人々の想いが桜に美しさを与えているのだといった感じで、作風に合う素敵な解釈がされておりとてもよかった。そして他にも、ソメイヨシノから関連付けられる、画一的な日本の教育形態。真の多様性とは、「人の欠点を欠点と認めて補い合うことではないのか?」などといった、あまり多様性が語られていない時勢に出版
powered by

レビューをもっと見る